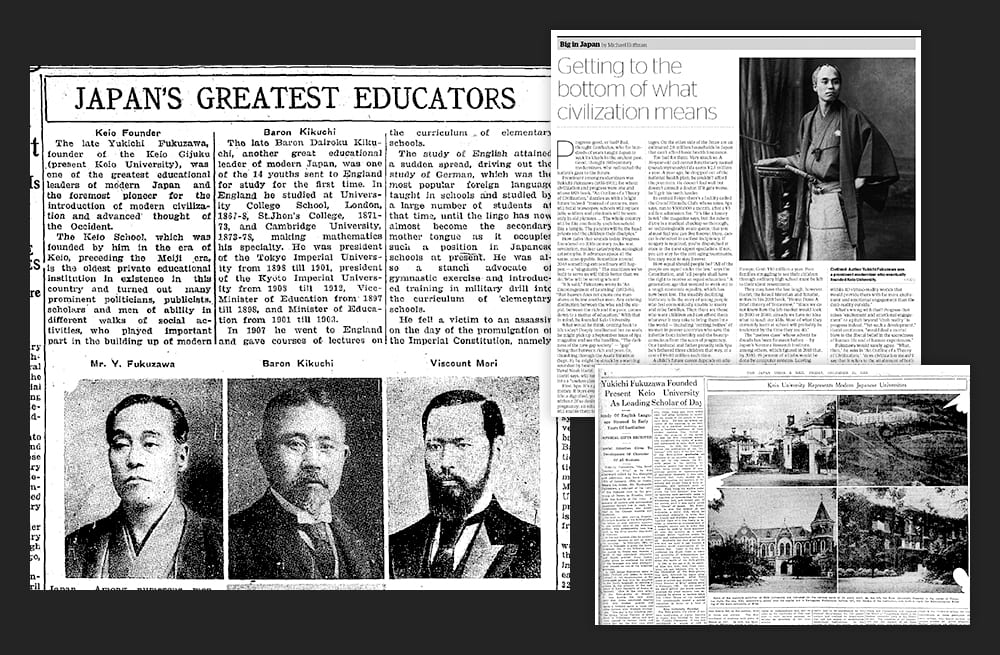August 29, 2025
相撲を取り巻く、伝統的な手仕事。

PHOTOS: MANAMI TAKAHASHI
相撲の起源を辿ると古事記などの神話にいたるが、国家安泰や五穀豊穣を願う神事としての歴史は、現在の大相撲に受け継がれている。本場所ごとに土俵に「相撲の神様」を招く儀式があり、伊勢神宮などでの奉納相撲は重要行事である。一方、エンターテイメントとしての相撲は江戸時代に確立する。相撲は歌舞伎と並ぶ二大娯楽となり、人気力士は熱狂的にもてはやされた。
その系譜で創設された相撲協会は、神事を司どる品格と江戸の粋を兼ね備えるように、力士の服装にも事細かに決め事を定めた。髪を伸ばして髷(まげ)を結うことを始め、普段の生活でも外出には着物の着用が必須だ。番付により細かい規定があり、十両、幕内の関取は大銀杏(おおいちょう)を結い、羽織袴や四股名を染め抜いた着物、名入りの番傘の使用が許される。その様子は、江戸時代に描かれた「相撲絵」そのままである。
大相撲は部屋制度で運営されており、力士のほか、元力士で指導役の親方、行司、呼出(よびだし)、床山(とこやま)などが、現在45ある部屋に所属し、大家族のように寝食を共にする。行司は土俵上の勝敗判定だけではなく、独特の相撲字で取組や番付を書き、場内アナウンスをするなど、多様な役割がある。装束や軍配は階級によって違いがある。
役割がさらに多岐に渡るのが、呼出だ。土と俵で土俵を作り、場所の開始や終了を告げる太鼓を叩く。取組の際には力士の四股名を読み上げ、土俵を箒(ほうき)で整え、力士が撒く塩を補充し、懸賞金の幕を持って土俵も回るなど、忙しい。階級はあるが装束は皆同じで、膝から足首まで細く仕立てられた裁付袴(たっつけはかま)に扇子を刺した粋な姿は、土俵上でも映えがいい。
表には出ないが、力士と切り離せないのが髪を整える床山である。髷は力士の象徴であり、引退時に断髪するまで、力士は毎日床山に髪を結い上げてもらう。関取は取組時などに、髷の端をイチョウの葉のように開いた大銀杏に結い直す。大相撲の独特な風習や制度を守り続けるには、こうした人々の存在が不可欠なのである。
力士が身につける品や土俵周辺の道具など、伝統的なものづくりを続ける職人たちも、大相撲を支える縁の下の力持ちだ。髷を結うには特別な櫛や鬢付け油、髪を結ぶ元結が必要となる。力士が締める締込、それを収める明荷、土俵を整える箒、力士が撒く塩を入れる塩籠など、いずれも天然素材を用い、手間ひまかけて丁寧に作られたものである。
以前は親から子へ、師から弟子へと継承されてきた手仕事だが、安価な輸入品やプラスチック製品に押され、全国的に昔ながらの工芸や手仕事は危機的な状況にある。自分の代で最後という高齢の職人も少なくない。ものづくりに欠かせない良質な天然素材の確保も年々難しくなっているという。国内外から弟子入り希望の問い合わせはあるものの、経済的にも体力的にも受け入れは難しいと皆口を揃える。
今年は相撲協会創設100周年である。この間、大相撲の伝統が守られ発展してきたのは、体系的な制度が整っていることに加え、海外からも力士を受け入れてきたためだろう。代々引き継がれてきた手仕事は、持続可能な地球のための叡智であり、海外でも高い関心を集めている。国籍にこだわらず後継者を育てる制度など、伝統的なものづくりへのより積極的な支援は、待ったなしの課題に映る。
櫛
力士の髷を結うの欠かせない4種類のつげ櫛は、創業1903年名古屋の櫛留商店が製造。三代目の森信吾と四代目の森英明が自宅工房で丁寧に作り上げる。1年ほど陰干ししたつげの板を、庭の窯で燻しては乾燥する作業を3−5年繰り返した木目に煙が染み込んだ板を使用する。鉋や鋸で切り出し、櫛の歯を立て、最後はトクサを乾燥したもので1000回ほど磨き「歯の一本づつに血の通った」櫛は出来上がる。

箒
土俵では大きめの竹箒と東京型と言われる座敷箒の2種が使われる。現在、後者は輸入物だそうだが、栃木の都賀の荒木時三商店では東京型箒の製造を続けている。農家の副業として箒作りが盛んだった地区だが、今はこちらだけ。材料のホウキモロコシを作る農家も高齢化で先行きは暗い。一度煮て乾燥させた材料を水に浸して、1週間かけて編んでできる箒は頑丈で美しい。50年は使えるとなればコスパも最強だ。

締込
力士が腰に締めるまわしは、稽古用や幕下以下の力士用は木綿製だが、関取の取組用は絹製の「締込(しめこみ)」である。現在唯一手織りで締込を織る職人は、滋賀県にあるおび弘・山門工場の石井一信で、後継者はいない。15,000本の経糸を2本づつ立て、5種類の糸をよった緯糸を使い、10メートル前後の締込を織り上げる。頑丈だが肌触りがよく、品がいい光沢は丁寧な手仕事のなせる技。安青錦の締込もここで織られた。

鬢付け油
日本で唯一の力士用鬢付(びんつ)け油「オーミすき油」は1965年に島田秋廣が創業した島田商店が製造。二代目島田陽次を中心に家族4人で作業をする。工程はひまし油と菜種油と木蝋を合わせて鉄鍋で溶かし、適温まで冷めたら香料を投入して木の棒で練り上げる。台に移して型に入れて切り分け、梱包まで一気に作業を進める。独特の甘い香りはバニラなどをブレンドしたもので、大相撲に欠かせない魅力の一つだ。


塩籠
力士は土俵に上がると力水を受け、塩を掴んで土俵に撒く。一連の儀式は土俵と力士の心身を清め、安全を祈願するものだ。塩を入れるカゴは塩籠と呼ばれ、現在、茨城県で職人が一人で製作する。真竹を使って編み上げる素朴見た目だが、底の部分には厚めの竹、縁にはラタンを巻いて補強がしてある頑丈な作りだ。本場所中、1日に使われる塩の量は40ー50キロ。塩籠に塩を補給するのは、呼出の仕事になる。