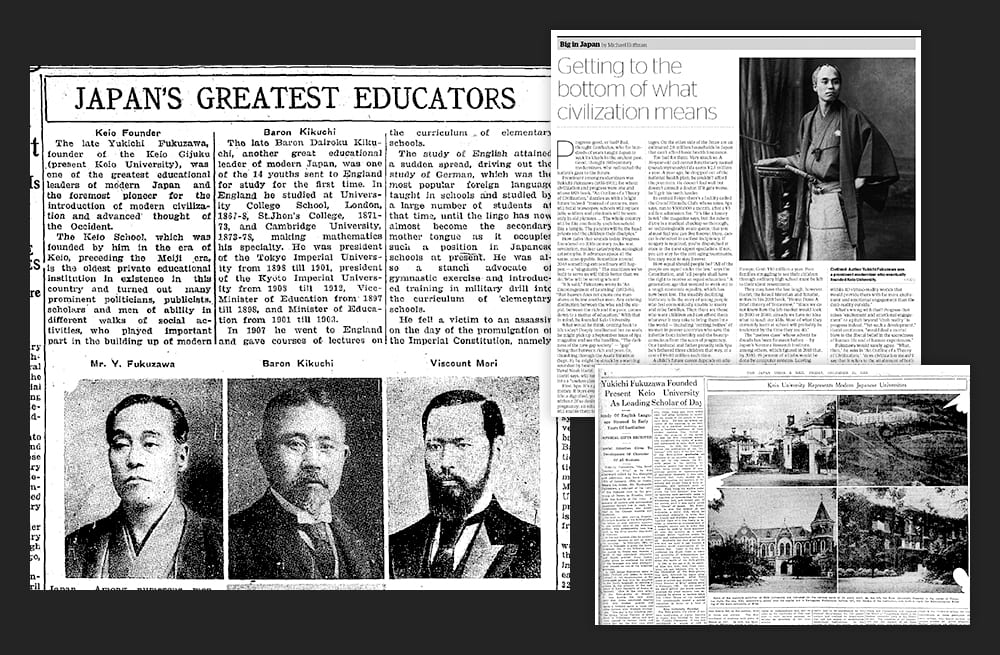October 24, 2025
【ソフトバンク】通信キャリアの枠を越えネットゼロへ挑む
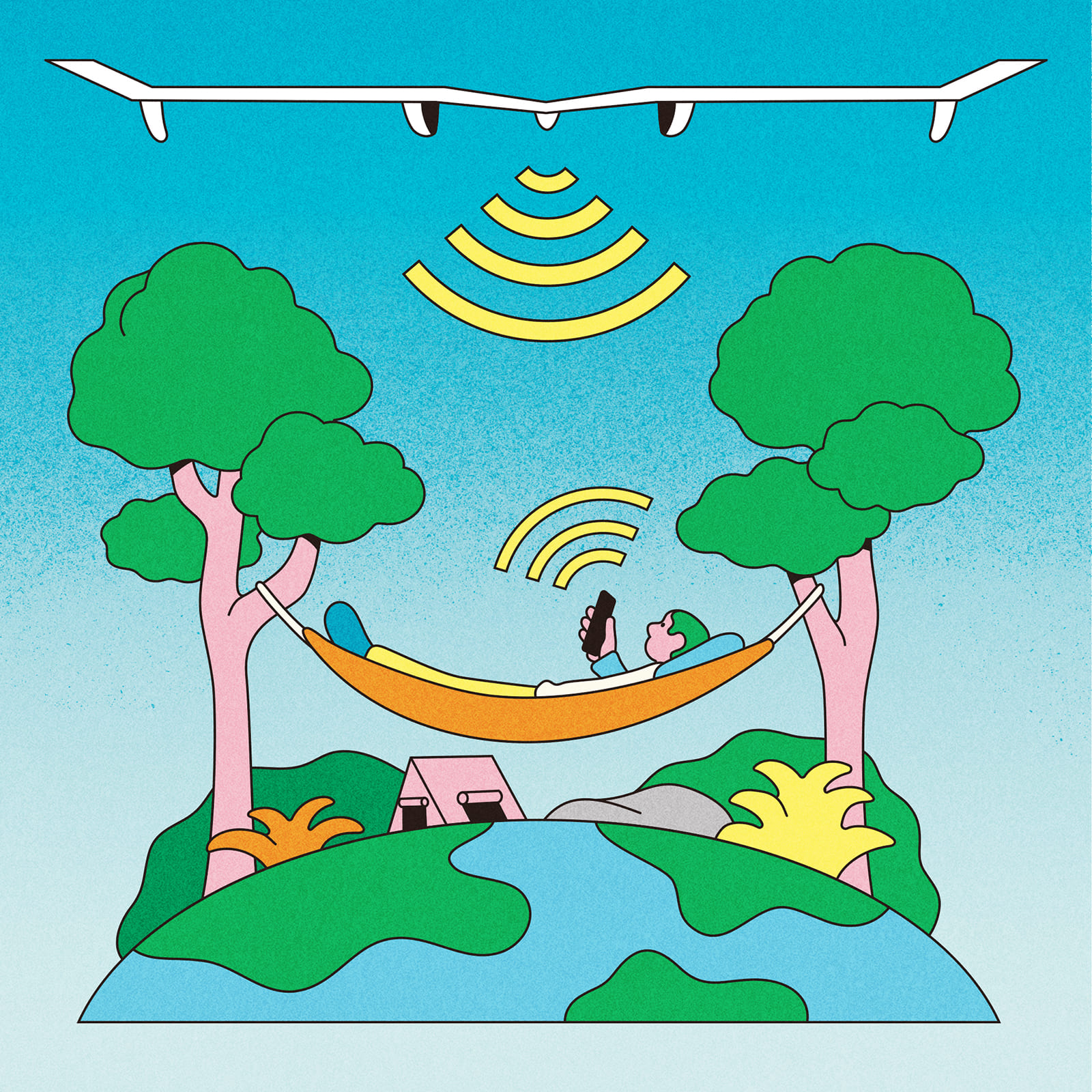
SoftBank’s strong points
1.2021年、宮川社長新体制になってからサステナビリティ経営を加速。
2.「日経SDGs経営大賞」を2年連続受賞のほか、「DJSI」でも高評価。
3.再生可能エネルギーの調達を前提とした大規模データセンターを設置。
4.半導体やAI通信関連の技術開発でScope3の削減にも寄与していく。

国内3大通信キャリアの一角、ソフトバンク。国際非営利団体「CDP」が公表した気候変動部門の「Aリスト」2024年版には、NTTドコモの親会社であるNTTとKDDIの2社が名を連ねるが、ソフトバンクの名はない。
3社はいずれもカーボンニュートラルやネットゼロを宣言し、サステナビリティ対応を強化している。
2020〜21年にかけて3社とも温室効果ガス(GHG)のScope 1・2を「2030年までに実質ゼロ」にする目標を掲げた。Scope3を含めて「2050年までにネットゼロ達成を目指す」と最初に踏み込んだのはソフトバンクだが、その後に追随したKDDIとNTTドコモはソフトバンクより10年早い「2040年までにネットゼロ達成」とした。
ソフトバンクだけがやや遅れをとっているように映るかもしれない。だが、同社は全力でサステナビリティに取り組んでいる。これらの事実だけでその“本気度”を測ることはできない。
「DJSI」「FTSE4Good」で通信キャリア首位
2024年11月、ソフトバンクはSDGsに貢献する先進企業を選出する「第6回日経SDGs経営大賞」を2年連続で受賞。上場企業887社を対象とした「日経サステナブル総合調査」に基づくもので、2年連続での大賞は初の快挙となった。
日本経済新聞は同時期に、脱炭素企業ランキング「GX500」も発表。ここでもソフトバンクは2023年に引き続き2年連続で1位を獲得した。再生可能エネルギー(再エネ)比率が2023年度に51%と、3年で32ポイント上昇したことなどが高く評価された。NTTは4位、KDDIは9位といずれも上位だが、ソフトバンクが頭一つ抜けた格好だ。
実際に2023年度の再エネ比率はNTTが42%、KDDIが29%で、ソフトバンクが首位。24年度、同社はさらに再エネ比率を61%まで高めリードを維持している。
グローバルでの評価も高い。ESG投資指標「Dow Jones Best-in-Class Indices(DJBICI)」の2024年版では、世界の上場企業321社が「World Index」に選出され、ソフトバンクは3年連続で名を連ねた。日本企業は37社。その中で「通信サービス」産業グループに属するのはソフトバンクだけである。
さらに、同年には「FTSE4Good Index Series」においても5年連続で構成銘柄に選定され、日本企業で最高スコアを獲得した。CDPの評価とのギャップが際立つ。その理由を、ESG推進室長を兼ねる池田昌人 CSR本部長はこう語る。
「2021〜23年まで、CDPの気候変動は『A-』評価。24年版でいよいよ『A』を狙っていたのですが、近年、回答様式が変更されたことから、記載に齟齬があり『B』になってしまった事情があります」
一方で、CDP以外の評価が高い理由を、ソフトバンクでサステナビリティ戦略も担当する青野史寛 専務執行役員兼CHROはこう説明する。
「2021年4月に宮川(潤一 社長兼CEO)へと体制が変わって以降、サステナビリティを経営の“ど真ん中”に据え、新たな事業と一体で推進してきたことが評価されているのだと思います」(囲み記事を参照)
背景には、宮川社長の強い危機意識がある。池田本部長は5年ほど前、宮川社長とサステナビリティ対応で議論した際のことをこう振り返る。
「宮川から『AIやIoTでデータが爆増する中、どれだけの電力が必要か想像できるか』と問われ、答えに詰まると、『ざっと大型火力発電所6〜7基分の電力が必要になる』と返されました。データ通信の使い放題が当たり前になりAIの利活用も進む中、本当にこのままでいいのかという宮川の危機感が原点だった気がします」
飛び交うデータと必要な電力は間違いなく増える。ではどうすべきか。具体的かつインパクトある取り組みが始まった。


AI-RAN antennas are being developed by SoftBank with international partners to distribute AI processing for phones and save energy.
COURTESY: SOFTBANK CORP.
「地産地消」型のグリーンデータセンター
宮川新体制になった翌月の2021年5月、ソフトバンクは温室効果ガス(GHG)のうち自社由来のScope1・2について2030年度までに実質ゼロにする「カーボンニュートラル宣言」をすると同時に、「再生可能エネルギー(再エネ)100%を目指す」とした。
Scope1・2の約6割は、約23万箇所に張り巡らされた携帯電話事業の基地局によるもの。まずはこの基地局すべての“再エネ化”を加速させるためにも、子会社のSBパワーを通じた再エネ電力の長期PPA(電力販売契約)による調達を急いだ。
2023年5月の決算発表で、年間20億kWhの再生可能エネルギー調達を20年間の長期契約で締結したと発表。2030年までに純粋な再エネによる発電の電力を50%に高め、さらに再エネ指定の「非化石証書」を組み合わせることで再エネ比率を“実質”100%とする道筋をつけた。
ただし、その先のゴールは証書を使わない純粋な再エネ比率100%。しかも、グループはAIを活用する大規模データセンターの構築を計画しており、基地局分だけの調達では間に合わない。そこで打ち出したのが、再エネありきのデータセンターである。
2023年11月、ソフトバンクは北海道苫小牧市に敷地面積が国内最大規模の70万平方メートル、50メガワット(MW)規模のデータセンターの開業を2026年度に目指すと発表。その電力を北海道内で発電された再エネで賄う「地産地消」型のグリーンデータセンターとして運用するとした。
将来的に受電容量を約10万世帯分の電力消費量に相当する300MW超まで拡大させる計画だが、「再エネの確保がない限り拡大させない」と池田本部長は言う。「新たな大規模データセンターは、グリーン電力の調達ありきのプロジェクトなのです」。
ほかにも大規模データセンターを北海道のもう一箇所と、関東、関西、九州に分散配置していく計画だが、いずれも地域内での再エネの確保を目指すという。
ビジネスより再エネ確保を優先する姿勢に、カーボンニュートラル・ネットゼロへの本気度がうかがえるが、ソフトバンクの取り組みは再エネ化にとどまらない。
革新的なAI処理基盤「AI-RAN」
同社は、「消費電力を下げる」テクノロジーの開発にも注力する。再エネの調達だけでは、膨大なScope3を削減することができないからだ。
2023年度、ソフトバンク及び主な子会社が排出したGHG排出量はCO2換算で年間約98万トン。その約95%がスマートフォン(スマホ)や通信関連の部材調達、スマホの使用など、サプライチェーンの上流と下流で生じるScope3である。
基地局やデータセンターの再エネ化を進めたところで、そのインパクトはGHG全体の最大5%。Scope3の大部分を占めるスマホの調達先などと協調したサプライチェーン革命、あるいはバッテリー革命を起こさない限り、CO2排出の根源を絶つのは難しい。
しかもスマホの消費電力は、AIの実装など高機能化によって年々上昇傾向にある。通信キャリアだけの努力でどうにかなる問題ではない。それでも、青野執行役員は「ダイレクトに当社がスマホを変えていくのは難しいかもしれないが、できることはある」と言う。
その一つが半導体チップへのかかわり。ソフトバンクの親会社であるソフトバンクグループ(SBG)は傘下に半導体設計を手掛ける英アームを抱えている。「スマホ搭載チップの99%がアーム設計によるものと言われています。チップの省電力化に寄与することで、世界中のスマホに影響を与える可能性はある」(同)。
今後の消費電力増大の主な要因であるAI処理でも、ソフトバンクはGPU大手の米エヌビディアなどと提携し、研究開発を進めている。消費電力を抑えた最新チップを活用したAIデータセンターを構築しているほか、2024年2月には通信・AI関連のトッププレイヤーとともにグローバルな業界団体「AI-RANアライアンス」を設立した。
ソフトバンクを中心に、エヌビディアやアームのほか、米アマゾン・ウェブサービス(AWS)や米マイクロソフト、フィンランドのエリクソン、韓国サムスン電子などが参画する壮大なもの。AIと携帯電話網の基盤である「無線アクセスネットワーク(RAN)」を融合させた革新的なAI処理基盤「AI-RAN」の構築を目指す。
前述の苫小牧のAIデータセンターのような大規模施設と、数十万箇所の無線基地局に設置されたAI処理基盤を有機的につなげ、AI処理を分散させる試み。すべての処理をデータセンターに依存するとそれだけ遠距離通信のための電力が必要になるほか、通信の遅延も生じる。無線基地局と処理を手分けすれば、無駄な通信を省き、全体の消費電力や遅延を抑えることが可能という。
昨今はスマホの高機能化で、クラウド側ではなく手元のスマホ側である程度のAI処理をさせるトレンドもある。ただ、AI処理は負荷が高く、スマホの消費電力も上がる。
これを、再エネで稼働する基地局側で代替できれば、「スマホ自体の消費電力を抑えることにも寄与できる」と池田本部長は話す。「私たちはこのAI-RANに、処理能力の向上もさることながら、通信網を省エネに導くキーテクノロジーとしても期待しています」。
ソフトバンクが取り組む未来へ向けた技術開発は、ほかにも多岐にわたる。
省エネにもつながる「空飛ぶ基地局」
高度約20㎞を飛行する成層圏通信プラットフォーム「HAPS(High Altitude Platform Station)」は、同社が2017年から実現に向けて開発を進めている「空飛ぶ基地局」。バッテリーとソーラー発電で成層圏を浮遊し、地上基地局を張り巡らすよりも低い電力で約200kmの範囲をカバーできる。早くから取り組むソフトバンクはこの分野で世界有数の特許を取得している。
衛星に比べ、地上との距離が近く、低遅延。離着陸を繰り返す定期メンテナンスも可能だ。都市部や建物内などすべての基地局を置き換えることはできないが、人の少ない山岳地域や牧草地、海域などにおけるIoTや緊急連絡、あるいは災害時の代替手段として期待されている。2023年9月には成層圏からの5Gの通信試験に世界で初めて成功。現在は気球型の無人航空機も開発中で、商用化を一気に早めようとしている。
一方、2021年には「ソフトバンク次世代電池Lab.」を設立し、次世代電池の開発を通じた環境負荷軽減も模索している。世界中のあらゆる次世代電池の評価・検証を行っており、2021年10月には米Enpower Greentechと共同で、質量エネルギー密度が従来の電池比で約2倍以上となるリチウム金属電池の実証に成功した。
手元のスマホから基地局、さらには成層圏まで。あらゆるロケーションで省エネ化につながる技術開発を進めるソフトバンク。まさに通信キャリアの枠を超え、2050年のネットゼロというゴールに突き進む。池田本部長は言う。
「正直、ネットゼロに至るまでの明確な根拠や道筋があるわけではなく、目指すんだという意思や約束を示す“宣言”に過ぎません。だから、あえて競合他社の『2040年』という目標に追随することもしていませんが、“本気度”では負けていないつもりです」
東京大学グローバル・コモンズ・センター(CGC)が企業とともに日本全体の脱炭素・ネットゼロを達成するための政策を議論する「ETI-CGC」という産学協創プラットフォームがある。ここにソフトバンクは通信事業者唯一の設立メンバーとして参画している。
「そこでもまだ答えは出ていません。でも、『じゃあそちらはどこまでできるの』とみんなが膝詰めをして、アクションを積み重ねていくしかない。我が社だけがネットゼロを達成するということはありえません。全員で模索していかないと日本全体のネットゼロは達成できない。そういう気概でETI-CGCに参加しています」
ネットゼロへ至る道筋は、まだ霧の中にある。それでもソフトバンクはその不確かさごと引き受け、歩みを止めない。未来を動かす原動力となるのはその“姿勢”なのかもしれない。

COURTESY: SOFTBANK CORP.
サステナビリティは成長戦略のど真ん中
青野史寛
専務執行役員 兼 CHRO
なぜソフトバンクはサステナビリティに本気で向き合っているのか。一言で答えるならば、「会社の将来・未来への成長戦略と一致しているから」という言葉に尽きます。
単なる通信キャリアではない「ビヨンドキャリア」を目指す過程で、2021年4月に宮川(潤一)が社長執行役員兼CEOに就任し、改めて、ソフトバンクがどう中長期で成長していくかの成長戦略を描きました。
今後の成長分野である「人工知能(AI)」や「モノのインターネット化(IoT)」などともっと本気で向き合うと、データが膨大になり、より莫大な電力を使うことになる。必然と、再生可能エネルギーの取り入れや、電力調達を考慮した地方分散もセットで考えなければならないということで、サステナビリティへの取り組みも戦略の大きな柱に据えました。
ですから、なにか数値が低いから改めなくてはならないとか、手を打たなければならないとか、そういったモチベーションではありません。サステナビリティへの取り組みは成長戦略そのもののど真ん中にある感覚であり、会社が長きに渡って存続していくために、事業とセットで考え、行動しなければならないという認識です。
そうした取り組みへの外部からの高評価も嬉しく思いますが、社内の若い世代から受け入れられていることも非常に喜ばしく思っています。
人事部門が従業員に対して実施している「エンゲージメントサーベイ」では、「自分の業務がESGとつながっている」と答えた従業員が2020年度上期に比べ、2023年度下期は約2.5倍に増加。結果として会社へのエンゲージメントも向上しています。
我々のサステナビリティへの取り組みがどう株価に反映し、収益にどう繋がっているのか、正直、わかりません。ですが、古臭い表現かもしれませんが従業員の「愛社精神」に繋がっていると明確に言えます。これも、我々が存続していく上で非常に大切な要素です。
社会のインフラを作るという大事な役割を担う我々にとって、社会の根幹とも言える地球環境を始めとするサステナビリティへの取り組みは責務です。ただ、そもそもソフトバンクには創業来、「情報革命で人々を幸せに」という理念があります。
スマートフォンをどんどん普及させて、どんどん世の中を便利にしていくというのも我々のビジネスでは大事ですが、一方で、シニアの方々などのデジタルデバイドを無くしていったり、脱炭素社会へ導いたりすることも、必然と事業とセットで考えていかなければならない。
じゃないと、人々は幸せにはなりません。我々の理念は実現できないのです。