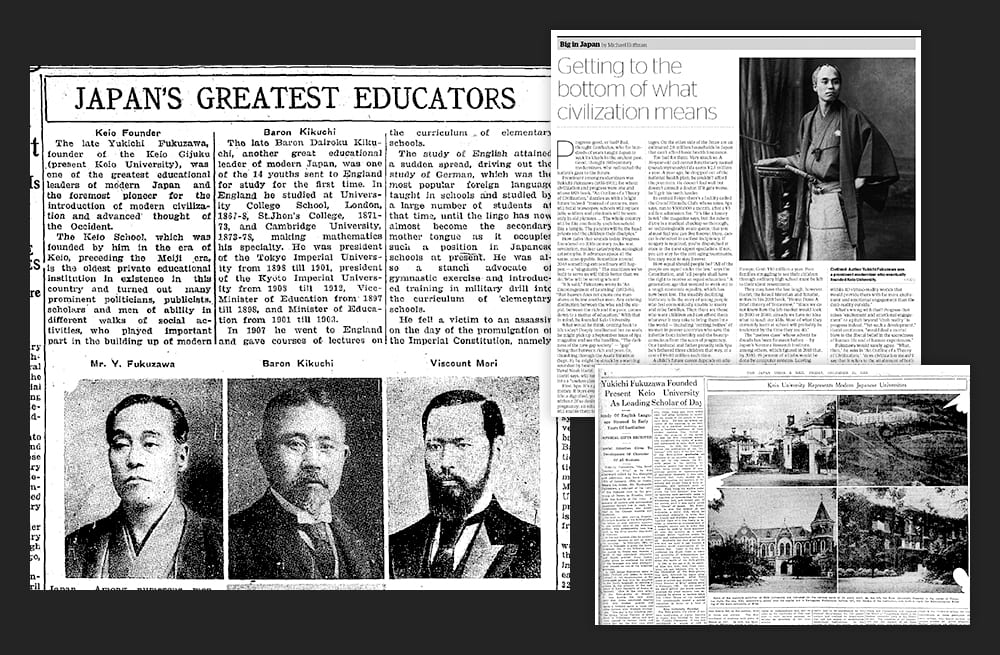August 18, 2020
地方の地域社会、成長の鍵は都市の人材(Satoyama推進シンポジウム2020 &「進化する里山資本主義」出版記念イベント)

地域外の人が農村の地域社会と産業に参画することは、活性化に効果的である。同時に、農村、山、海には地域外の人だからこそ、そこに価値を感じるような地域資源がもともとあり、それらを利用しなければ実現できないこともある。
「新しいことに挑戦する熱意のある人と、漁業において革新的な変化が起こっている地域とを繋ぎたいと思っています」と、東京を拠点とするNPO法人ETICの伊藤順平氏は5月29日にジャパンタイムズ里山推進コンソーシアムが開催したオンラインシンポジウムで話した。
このシンポジウムでは、伊藤氏と宮城県石巻市にある一般社団法人フィッシャーマン・ジャパンの松本裕也氏が、スキルを持つ都会の人と地方の漁業を繋ぐ現在進行中のプロジェクトについて語った。
昨年、ETICとフィッシャーマン・ジャパンは共同で、意義のある副業を探している都市部人材と水産事業者とを繋げるギョソモン!というサービスをスタート。ギョソモンは「漁業」と「よそもん(よそ者)」をかけた言葉だ。
人と人、人と地域、そして人と、地域の発展を支えて社会問題を解決し新しい価値を作れる起業家マインドを持ったリーダーを育てるプロジェクトとを繋ぐことがETICの核となる活動だ。
2014年に設立されたフィッシャーマン・ジャパンは、2011年の東日本大震災で大きな被害を受けた漁業の活性化を目指している。松本氏は、「目先の利害関係にとらわれず、将来に目を向けられる人を外から入れることは重要です」と語った。
松本氏自身も、ヤフージャパンの社員を続けながら、地震後に石巻にやってきたよそ者だ。「水産物は日本が保有する数少ない資源のひとつであり、漁業という文化は守らなければなりません」と松本氏は述べ、国家の危機を救うのは必ずしもお金ではないと強調した。
この考えは、2013年に出版された「里山資本主義」という本の中で紹介された里山資本主義の概念と合致している。この新しい形の資本主義は、里山(地域住民によって手入れされている森林)や里海(地域住民によって手入れされている沿岸部)の既存の天然資源の利用を中心に据えている。
活気づく漁業
ギョソモン!は漁師の育成プログラムを開発し、新商品のブランディングをするなどのプロジェクトを実施することを支援したり、日本中から必要なスキルや知識を持った人にパートタイムで参画してもらうことで漁業を活気づけることを目指している。
「フィッシャーマン・ジャパンが地元の漁師たちがプロジェクトを計画するのを助け、ETICはそれらのプロジェクトに参加したい人を集めています」と伊藤氏。
「参加者は、基本的に打ち合わせも仕事もオンラインでこなします。賃金は季節の魚という形で支払われます。月1回の訪問の交通費も支給しています」と松本氏は述べた。
松本氏は、地元住民以外の人々が関わることは、漁師たちに無いスキルを提供する以上の良い効果をもたらすといい、また外部の人は現在のビジネスモデルを俯瞰して理想的なあり方を考えることができ、これは特にプロジェクトの準備段階において助かったと語った。
地元住民と都市住民を結ぶ
様々な場所から様々なステークホルダーが協力して一つの地域を活性化する成功例を作るには、「地域住民とよそ者の間のコーディネーターとして機能できる人または支援グループが必要です。それは、地域の慣習や関係性、特徴を十分に理解している人である必要があります」と伊藤氏。
地域のプロジェクトに地域外の人が参加することは、同じシンポジウムの一環として翌日行われたトークセッションでもテーマの一つとして取り上げられた。このトークセッションでは、木を扱う職能集団、ようびの大島奈緒子氏とちりめんじゃこを専門とする水産・加工会社の石野水産の石野智恵氏が登壇し、地域資源を活用したユニークな商品作りについて語った。
大島氏も、もともとよそ者だった。 10年ほど前に岡山県西粟倉村に移り、現在ようびの代表取締役を務める夫の大島正幸氏とともに、主に地元のスギやヒノキを使った家具を作る工房をスタート。
そういった針葉樹林は日本各地にあり、その多くは将来の需要に応えるために50年以上前に植林された。しかし、林業の後継者不足や所有者の高齢化などにより、手付かずで放置されている森林もある。さらに、近年、安価な輸入木材が市場を席巻し、国産の木が使われないままになっている。
木が密集して生えた状態では、若い木や土壌を豊かにしてくれるその他の植物の健全な成長が妨げられてしまう。大島氏によると、土壌がやせていると地下水をためることができず、洪水や地滑りを起こす原因にもなるという。
「こういう森の存在が災害のときだけニュースになるというのは切ないです」と大島氏。
豊かな資源、地元のサポート
豊富な森林資源と地元住民の温かい支援のおかげで、ようびの事業は成長し、現在では、建築やリノベーションなど多方面に広がった。しかし、苦労がなかったわけではない。 2016年には火事で工房が全焼した。大島氏やようびのチームが、友人や隣人、顧客、支援者の力を最も感じたのは、火事の直後だった。
「私たちが作ってきたもの全てが灰に変わったのを見るのは辛かったです。しかしメンバー全員が現場に集まるとすぐに、大島正幸代表はここに工房を再建すると宣言したのです。その言葉で、前だけを向くことができました」と大島氏は語った。
再建の決意
大島正幸代表の迅速な決意表明の背後には、いつここに戻ってきても歓迎すると彼がすべての顧客と交わした約束があったからだと大島氏はいう。再建中、全国から集まった何百人もの人々、そして村の人々がようびを訪れ、作業を手伝った。「微力は無力ではない。」これは大島氏がこの体験を通じて学んだ真理だった。
大島氏が移住者であり起業家として西粟倉に拠点を置いたのに対し、石野水産の石野氏は、広島県呉市の鹿島で90年続く家族経営の事業に加わるために故郷に戻ったという経歴だ。
石野氏は10代で故郷を離れ大学を卒業後、メーカーとコンサルティング会社に勤務していた。その後、彼女は外からの視点とスキルを持って故郷に戻った。
石野水産は、特にマーケティング、包装、販売における彼女のアイデアとスキルを活用することで、問屋などへの原料の卸しではなく、小売店や通販など、直接消費者に販売する水産・加工会社の成功例となった。
「炊いたひじきも販売しています。これは、乾燥させた商品よりも足が早いので、顧客と直接つながる私たちのような小規模な生産者でなければ無理です。大手メーカーは、いろいろな場所や生産者のひじきを使用しているため、安定した品質を提供できません」と石野氏は語った。
石野水産では、玉ねぎ、みかん、レモン、そら豆など、代々続く自社の畑で育つ野菜も販売している。
「自分たちで責任を持つことができる、価値ある季節の産物を販売しています」と石野氏。また、販売にはオンラインプラットフォームも活用していると説明した。新型コロナウイルスによる危機的な状況の中、石野氏は自身のノウハウとネットワークを活用して、地元のバラの生産者が直接個人に販売するのをサポートした。
日本の農村地域の多くは豊富な資源に恵まれているが、それらを利用するために必要なスキル、知識、または人材まで揃っているとは限らない。シンポジウムで共有された事例などのように、都市部にはもっと有効活用し得る技術や人材がある。