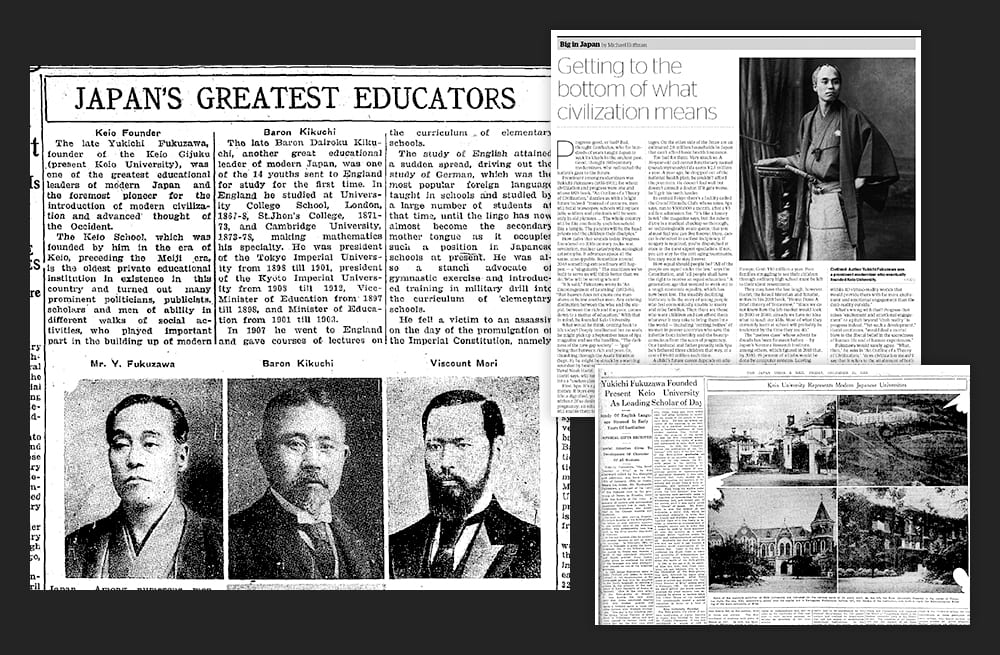March 25, 2022
江戸文化研究者・田中優子に聞く、江戸の暮らしに学ぶサーキュラーエコノミー

1952年生まれ。江戸文化研究者。法政大学社会学部教授を経て2014年〜2021年まで同大学総長を務める。現在は同大学江戸東京研究センター特任教授。代表著書に『江戸の想像力』など。 | PHOTOS: KOUTAROU WASHIZAKI

江戸時代の日本社会において、生活ゴミはほとんど出なかったという。いまでは廃棄されてしまう生活道具や衣服も、当時は何度も補修して使い続け、ときには形を変えてリユースを繰り返していた。一見すると無用なものでも、まだ役に立つ価値があり、捨てるには惜しい。そんな思いを、日本語では「もったいない」と表現する。
ノーベル平和賞を受賞したケニアの環境保護活動家のワンガリ・マータイ氏は、2005年に京都議定書の関連行事で日本を訪れた際、初めて知った「もったいない」という日本語に感銘を受けたという。この言葉には、リサイクルやリユースという視点だけではなく、自然やモノに対する尊敬の念も込められているとマータイ氏は考え、「もったいない」を世界共通言語にしようとアピールしていった。

何度も洗濯できない着物は、毎日の手入れが重要になる。小さな汚れはお湯で落とし、湿気の多い日は干して乾燥させるなど、一枚の着物を長く使い続ける工夫がなされていた。 | ILLUSTRATIONS: ROMI WATANABE
しかしなぜ、日本でこうしたユニークな言葉が定着したのだろうか? その背景を知るべく、江戸時代の生活文化に詳しい江戸文化研究者の田中優子に話を聞いた。インタビューを行ったのは、東京・六本木にある<国際文化会館>。1955年に国際的な文化交流を行うことを目的にロックフェラー財団の寄付金で建設され、前川國男、坂倉準三、吉村順三という日本モダニズム建築を代表する建築家3人が共同でつくりあげた非常に珍しい建築である。2004年頃には施設の老朽化や財政危機に伴って取り壊しが検討されたが、さまざまな関係者の努力によっていまも改修が重ねられ、愛されながら使われ続けている施設だ。日本の「もったいない」精神が垣間見える場所のひとつといえるだろう。
「工業化が進む前まで、生活で使うものはすべて再利用することが当たり前でした。なぜなら使える資源は有限でしたから、四季のある日本では、一年の自然のサイクルのなかでいかに資源と生産のバランスを取るかを考えてきたのです」。

古くなった着物は、糸をほどいて布状に戻し、布団のカバーや小物入れ、風呂敷などに仕立て直して再利用されていた。 | ILLUSTRATIONS: ROMI WATANABE
そう語る田中は、着物を例に江戸時代のリサイクルシステムを説明してくれた。「着物を着る際に、最も重要なのはお手入れです。たとえば今日わたしは母の着物を着ていますが、古くなった布地に新たな縞模様を染めて使っています。帯などは70年以上前のものなので、もう専門の業者でもほつれを修理できる技術を持つ人がいないと言われてしまいました。けれど、かつて着物を日常的に着ていた時代には、毎日の汚れを拭いて落としたり、ときには糸をほどいて数枚の布に分けてから洗い、仕立て直すようなことまで各自の家で行っていたんですね。それでも使えなくなった着物は、古着に出すこともあれば、子供の着物や布団カバー、モノを持ち運ぶ時に用いる風呂敷などにつくり直して使っていました。最終的にぼろぼろになった布は、かまどで燃やして灰にします。100年前まではどんな家にも炊事用のかまどがありましたから、灰にするのは簡単だったのです。さらには「灰屋」といって、この時出た灰すらも購入してくれる専門の業者もいました。灰は染め物の原料や肥料などに転用できるため、売り物のひとつとして重宝されていたのです」。
第二次大戦前までは、灰屋のような専門のリサイクル業者や修理業者が数多く存在したと田中は言う。「鍋や下駄、キセルなどの道具には、それぞれ作り手の職人以外に、壊れた部分を修理する専門の職人がいました。また日本では植物を原料とする手漉きの和紙が主流でしたが、使い古した紙を分解して、もう一度漉いてつくりなおす専門職もいましたね。現代のような生産と消費を繰り返すだけのサイクルではなく、ゴミを利用可能なものへと再構築する循環のシステムが成立していたのです」。

ぼろぼろになった布は、かまどで燃やして灰にする。100年前まではどんな家にも炊事用のかまどがあったため、食材などの小さなゴミはほとんど燃やしていた。 | ILLUSTRATIONS: ROMI WATANABE
このように、江戸時代には成立していたサーキュラーエコノミー(循環型経済)を、現代社会に取り戻すことはできるのだろうか? そこには、私たちの強い意思が必要だと田中は語る。
「これだけ多くのものを輸入に頼るようになったいま、現在のサスティナブルの問題は国や地域単位で考えても仕方がありません。かつては各地域で生産される資源だけが頼りでしたが、植民地支配によって他国から資源を収奪するようになって以来、人類は数百年の月日をかけて生産のサイクルから逸脱してきてしまいました。そうして、より多くのエネルギーや資源を求め続けているのが現在です。もう取り返しはつかないだろうと絶望的にもなりますが、それでも消費者である自分の取る選択肢として、むやみにモノを買いすぎず、ひとつ一つの道具と向き合い、徹底的に使い続けるという意思を示すことが重要です。さらには、古くからある着物だって、伝統に縛られず、現代風のドレスや着こなしにアレンジしたっていいと思います。今の生活に合わせて新たな工夫を重ねていく。そうした知恵の集積が、これからの社会の礎をつくっていくのではないでしょうか」。