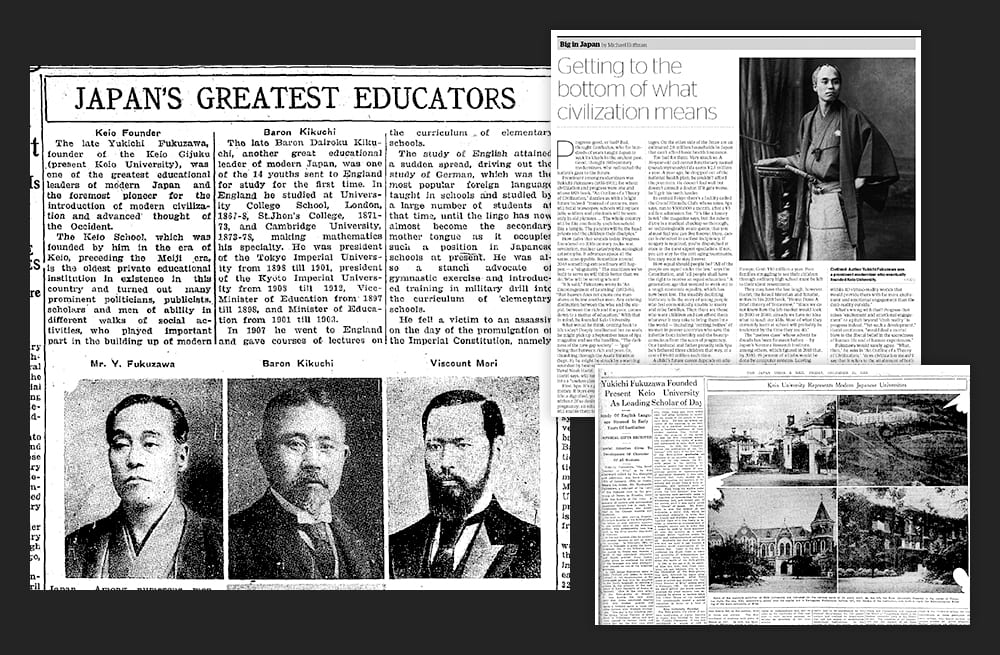November 29, 2021
アイヌ工芸をいまに継承する木彫り職人、瀧口健吾。

撮影/鷲崎浩太郎
アイヌでは、成人するまでに男は木彫りを習い、女は刺繍を習う風習があったという。アイヌ独自の紋様が刻まれた木彫りや刺繍などの美しい工芸品は、その一つひとつの模様に家族や過去にあった出来事などを表す意味があり、個々人のアイデンティティを示す象徴でもあった。こうしたアイヌ独自の工芸品を、いま現代にアップデートしようとする人々がいる。
その拠点のひとつが、雄大な湖と温泉街を有する釧路市阿寒町の文化施設「阿寒湖アイヌコタン」だ。この土地は元々、戦前に環境保全活動に取り組む前田一歩園財団がアイヌの人々の生活を守るため、店や住まいなどの土地を無償で提供したことから始まった場所だ。これをきっかけに北海道各地のアイヌがそれぞれの工芸や踊りなどの文化を持ち寄り、長らく観光客向けの事業を行ってきた。


撮影/鷲崎浩太郎
だが、これまでアイヌの人々の収益は観光客に向けた土産物の販売がほとんどで、それ以上の事業に発展することはなかったという。しかし1997年に公布された「アイヌ文化振興法」を皮切りに、アイヌ文化の継承者の育成や調査研究などの公共施策がスタートし、さまざまなアイヌ文化に関する交付金が下りるようになっていく。そうした背景から、阿寒町でアイヌ文化振興に取り組む一般社団法人阿寒アイヌコンサルンは、アイヌの工芸作家たちを紹介するプロジェクト「AKAN AINU ARTS AND CRAFTS → NEXT」を2020年から始動した。ここではアイヌの工芸品を伝統の型に押しこめず、現代の感性にも訴えられるものとして国内外のファッション企業やセレクトショップとのコラボレーションを推進している。
同プロジェクトに参加する作家、瀧口健吾は、木彫り職人だった和人の父とアイヌ人の母を持ち、現在は木彫り職人として活動しながら、アイヌ文化を伝える観光ガイドにも従事している。
「僕は今ま39歳ですが、阿寒では最年少のアイヌ作家なんです」。そう笑って話す瀧口も、一度はオーストラリアに移住し、アイヌ文化とは離れた暮らしをしていたという。100年近く続いた日本の同化政策によってアイヌ文化の継承は抑制され、アイヌの人々は周辺地域からの差別に苦しめられてきた。瀧口の世代では、アイヌ文化を親から受け継ぐような人はほとんどいなくなっていたという。

撮影/鷲崎浩太郎
「10年くらい前に、姉と北海道の各地をめぐる旅をしたんです。そのとき、あるアイヌの儀式を初めて目にして、これほどまでに自然と共に生きる文化があったのかと衝撃を受けました。自分にもアイヌの血が流れているのに、アイヌのことは何も知らなかったと痛感したんですね。そこから少しずつアイヌの文化について勉強し、アイヌの木彫りの講習にも通うようになりました。アイヌのものづくりの特徴は、素材をムダなく使うこと。たとえば木を削るときも未使用になった木片は土に埋めて、また苗木として再生できるような工夫を凝らしています」。
もうひとつのアイヌ工芸の特徴として、異文化からの影響があると瀧口は語る。「日本やロシアなど国境を超えて多数の地域と交易を行っていたアイヌでは、工芸品のなかに明らかに異国の文化を取り入れたと思える紋様が見られることもあります。そう考えると、アイヌの伝統文化とは、自然物を無駄にしないという根底の思想を保ちながら、常に変化していくものだとも捉えられると思いました。そういう思いもあって、いまぼくはフィンランドのサーミ民族の伝統工芸である「ククサ(KUKSA)」と呼ばれる木製のマグカップをつくっています。このカップにアイヌ文様を彫っているのですが、こうした異国文化とのコラボレーションも、これからのアイヌ文化として提案してきたいですね」。