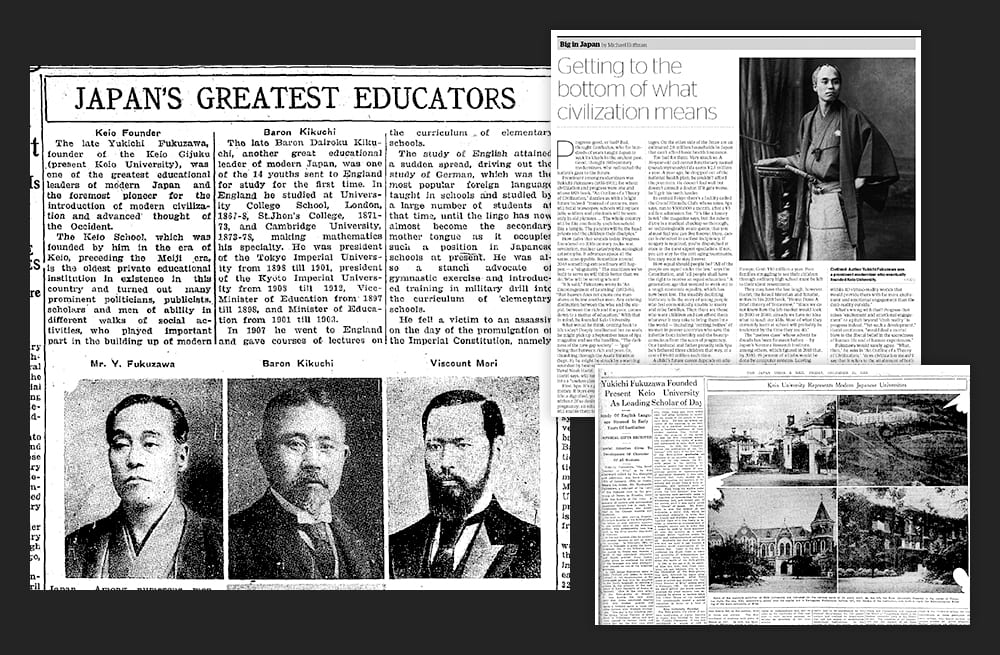October 24, 2025
料亭で出される伝統工芸の器。
海外から日本を訪れる人が、もっとも手軽に多種多彩な日本の伝統工芸品に触れられる場所といえば、料亭や割烹などの日本料理店が挙げられる。ゲストを迎える暖簾に始まり、部屋の建具やしつらえ、女将の着物、そして、料理を盛る器などに日本各地の伝統工芸品が使われているからだ。
高級な日本料理のルーツは、正式な茶会でお茶の前に出される「懐石」と呼ばれる食事にあるため、使用される伝統工芸の器も昔から茶人に好まれてきたものが多い。意匠には四季の花鳥風月を表したものや、鶴や亀など、古くよりめでたいとされてきたもの、長寿や幸運、永遠を象徴する吉祥文様、また、魔除けを意味する柄が選ばれる。基本的には、ひとつのコースで同種の器が重ならないよう、産地や作家、作風などを変えて料理を盛る。美術館に収蔵されるような名品は希少で市場にめったに出回らず、また非常に高価であるため、「写し」が作られる。石川県金沢市の料亭『日本料理 銭屋』でも、写しが多用されるが、それらもまた、時代や土地を代表する名工による貴重なものばかりだ。ふた付きのものはふた裏にも見事な意匠が施されていることが多く、見どころ満載。食べ終わった後、底に美しい絵が隠れていたことに気づくこともあるだろう。そして、温かな汁を張ったお椀を手に取り、唇に触れて、料理と一体になった状態を堪能してほしい。それが伝統工芸品たる、正しい日本の器の味わい方なのだから。

中国製ではあるが、日本の茶道の美意識によって選ばれ、日本の宝として後世に受け継がれてきたものが多い。中国・明末期(17世紀中頃)に景徳鎮にある民窯で焼かれた素朴な染付磁器。当時、現地では「青花」と呼ばれる普段使いの器だった。官窯と比べて素地が粗く、形や文様の不完全で自由なところが、日本の茶人に親しまれ、茶人が現地に好みのものを特注することもあった。
PHOTOS: NAOFUMI MIYAJIMA

石川県の伝統的な色絵磁器。1655年に加賀藩の支藩である大聖寺藩(現在の石川県加賀市)の藩主、前田利治が藩士に命じて、肥前有田(現在の佐賀県有田町とその周辺)で製陶技能を習得させ、殖産政策として作らせたのが始まりとされる。九谷五彩と呼ばれる青(緑)、黄、赤、紫、紺青の釉薬で描かれる、華やかで格調高い絵付けを特徴とする。写真の皿は江戸時代中後期のもの。
PHOTOS: NAOFUMI MIYAJIMA

江戸時代中期(17世紀後半〜18世紀中頃)に活躍した京焼の陶芸家・絵師であった、尾形乾山の技法や作風を写して作った焼物は大変人気で、現在でも盛んに作られている。明快な色使いやポップなデザインが特徴的で、コースの中にひと皿挟むだけで、場を華やかに盛り上げてくれる。写真は石川県金沢市の九谷焼の名工、初代・矢口永寿(やぐち・えいじゅ)が20世紀に写した菊花皿。
PHOTOS: NAOFUMI MIYAJIMA

江戸時代が始まる30年ほど前に、美濃(現在の岐阜県)で焼かれた白釉を用いた焼物。「卯花墻」という銘をもつ志野焼の茶碗は、国産の茶碗で2つだけ国宝に指定されたうちのひとつ。写真は京都・樂家12 代弘入(隠居後の名前)が、樂焼の土で、その色味から「鼠志野」と呼ばれる志野焼を写した向付(前菜用の器)で、秋草が描かれている。
PHOTOS: NAOFUMI MIYAJIMA

石川県を代表する茶道用の焼物。1666年、加賀藩主5代、前田綱紀が京都より茶道・裏千家4代家元の仙叟宗室を金沢に招聘した際、京都の樂家4代一入(隠居後の名前)の高弟であった、初代長左衛門が同道し、茶碗などを金沢郊外の大樋村で制作したことに始まる。写真は6代長左衛門による、艶やかな茶色い“飴釉”が特徴の扇面形の向付(前菜用の器)。
PHOTOS: NAOFUMI MIYAJIMA

漆塗りは縄文時代にはあった技法で、青森県から沖縄県まで各地に産地がある。なかでも京都府や石川県で作られ、金銀箔で文様を施した蒔絵や青貝を用いた螺鈿などの加飾を施したものは高級品として知られる。写真のお椀は左から、蒔絵で菊を描いた京蒔絵、波千鳥の意匠を施した加賀蒔絵、朱塗に螺鈿の花を散らした輪島塗のお椀は戦国武将が作らせた「明月椀」写し。
PHOTOS: NAOFUMI MIYAJIMA

天正年間(16世紀後半)に陶工であった長次郎が「わび茶」を大成した千利休から指導を受け、樂茶碗を創出したことから始まる。京都・樂家の当主は代々、吉左衞門を名乗り、手びねりで作る茶碗をメインに懐石道具を含む食器も制作する。写真は11代の慶入(隠居後に名乗った名前)による、おめでたい向鶴をかたどった器。鮮やかな緑釉が美しい。
PHOTOS: NAOFUMI MIYAJIMA

江戸時代後期(19世紀頃)から現在まで江戸・東京都で生産される切子加工を施したガラス製品の総称。海外から持ち込まれたガラス製品に切子細工を施したのが始まりとされる。食器のほか、金魚鉢などの日用品がある。写真の皿は『日本料理 銭屋』先代主人が19世紀のガラス鉢のボヘミアンカットのデザインを、江戸切子の職人に写してもらった特注品。
PHOTOS: NAOFUMI MIYAJIMA