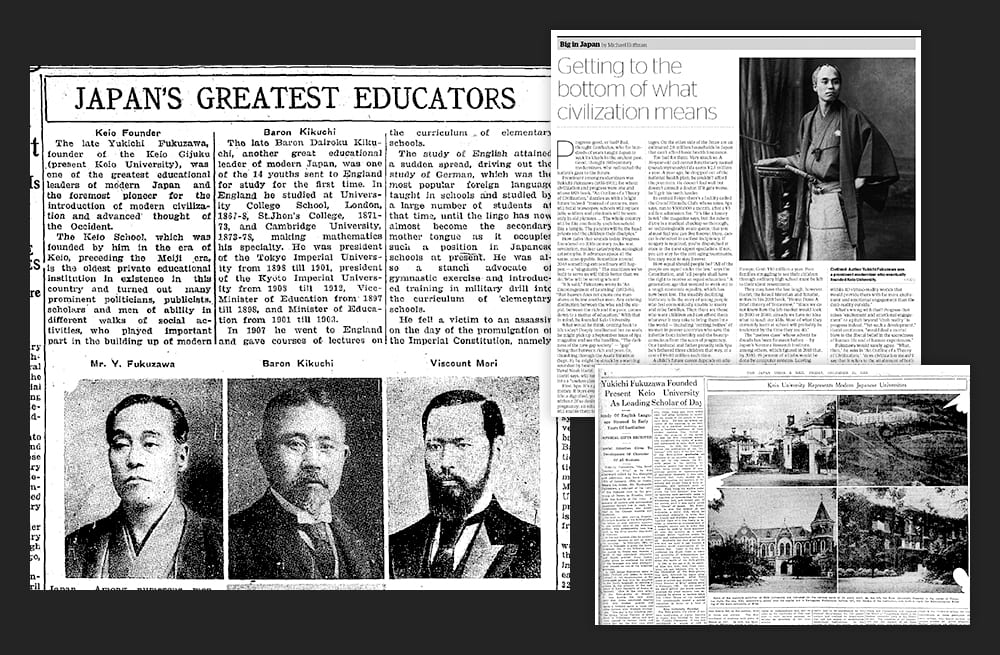February 25, 2022
建築家フランク・ロイド・ライトと、帝国ホテルを巡る物語。

COURTESY: IMPERIAL HOTEL
東京・日比谷。皇居からも近い東京の中心に日本を代表するホテル、帝国ホテルが建っている。創業は1890年。近代国家を目指す日本の「迎賓館」の役割を担う場として、政財界人らの働きかけによって生まれたホテルである。

COURTESY: IMPERIAL HOTEL
現在の建物は1970年代初頭にできたものだが、その前までは日本風とも西洋とも言えない、独特のデザインをした宮殿のようなホテル棟が建っていた。それが巨匠フランク・ロイド・ライト設計の、今は無き、通称ライト館と呼ばれる建物だ。
アメリカ人であるライトが、なぜ日本を代表するホテルの設計をすることになったのか? まずそこから説明したい。
ライトは建築家としてのキャリアをシカゴ派の巨匠として知られる建築家ルイス・サリヴァンの元でスタートさせた。サリヴァンの元を約6年で独立した後は、プレーリースタイルと呼ばれる、アメリカ中西部草原地帯の名前から命名した、水平が強調され大地と一体となったデザインの住宅を中心に設計をしていた。そんな建築家として活動するライトには知られざるもうひとつの顔があった。それはかなり本格的な日本の浮世絵バイヤーとしての顔だった。実はこの浮世絵がライトと日本を結び付けるきっかけとなる。ニューヨークの東洋美術商に勤務していた林愛作が、帝国ホテル七代目支配人として着任すると、新館建設の設計を浮世絵を通じ旧知の間柄だったライトに依頼したのだ。

COURTESY: IMPERIAL HOTEL
当時のライトは女性問題をはじめとしたスキャンダルに見舞われ信用を落とし、アメリカでの仕事は激減していた。そこに起死回生のチャンス、帝国ホテルの仕事が日本からもたらされたのである。そんなライトが生み出そうとした建築は、西洋と東洋、古代と現代が融合する、新しいタイプの建築だった。左右対称で横に客室棟が広がる姿は、どこか1893年に開催されたシカゴ博覧会でライト自身が出会った初の日本建築<鳳凰館>(京都・宇治の<平等院鳳凰堂>を模した日本パヴィリオン)を思わせる。建築が地面と一体でしっかり根付く様子はプレーリースタイルにも見え、その建築をマヤ・インカ文明の遺跡にあるような幾何学模様の付いた大谷石(東京近郊の栃木県で採掘される軽凝灰岩)やテラコッタが覆う。これはまさにライトの、既存の西洋建築のコピーは作らないという意気込みと熱意をもって設計に取り組む賜物であった。しかし、その思いの強さが裏目に出る。1921年竣工予定のはずが工期は大幅に遅れ、建設費も当初の倍近くに膨れ上がった。林愛作はライトを擁護するも、22年4月、初代本館が失火で全焼するとその責任を取って支配人を辞任。後ろ盾を失ったライトもその3か月後にアメリカへ帰国、二度と日本の地を踏むことは無かった。

ル・コルビュジエ、ミース・ファンデル・ローエと並んで近代建築三大巨匠と評される建築家。1867年、アメリカ・ウィスコンシン州生まれ。生涯で800を超える建築の設計を行う。代表作に、<落水荘>(1937年竣工)、グッゲンハイム美術館(1959年竣工)など。日本では、愛知県に<帝国ホテル玄関部分>(1923年竣工)が移築復元されている他、東京都に<自由学園明日館>(1922年竣工)、兵庫県に<ヨドコウ迎賓館(旧・山邑家住宅)>(1924年竣工)が残る。
© BETTMAN/GETTY IMAGES
その後ライト館の設計は弟子の遠藤新が引き継ぎ、1923年に無事完成する。完成披露パーティーの日にホテルは関東大震災に見舞われるが、「浮き基礎」と呼ばれる、東京日比谷の軟弱地盤地に対し基礎の杭を短くし振動を吸収するライト独自の工法が功を奏し、ほぼ無傷で済んだ。アメリカにいたライトはこの報告を受け、自伝で自身の建築の耐震性の高さを大いに宣伝した。帝国ホテル・ライト館は“東洋の真珠”と呼ばれ、日本を代表するホテルとして多くの賓客をもてなすこととなる。ライト館はその後太平洋戦争でも焼けず残り、戦後占領下ではGHQに接収されるなど数奇な運命をたどることとなる。
そして時は日本が高度成長の絶頂期にあった1967年3月。ライト館を壊し、新たに高層ホテルを建設することが新聞で報道されると、これを機にライト館保存の運動が展開されることとなる。その運動の中心になったのは日本の建築家を中心とした「帝国ホテルを守る会」で、時の総理大臣・佐藤栄作をはじめとした政治家へも働きかけ、建築の現地保存を訴えた。同年10月にはライトの妻、オルギヴァンナ・ロイド・ライトも保存活動のために来日し、ライト館取り壊しは国会でも取り上げられ、ある意味、日米問題にも発展した。
しかし、完成からまだ44年しか経っていないというのに、ライト館の老朽化は激しかった。関東大震災から建物を守った「浮き基礎」工法が災いともなり、建物の地盤沈下が激しかったのだ。解体直前のライト館は、中央1階事務所は半地下室にようになり、宿泊棟廊下はワゴンが使えないほど波打っていたという。帝国ホテル側は経済合理性を優先しあくまで解体・立替という考えに変わりはなかった。様々な議論の末、玄関部分のみが愛知県の<博物館明治村>へ移築・復元されることとなった。移築には莫大な費用がかかるため明治村も難色を示していたが、初代館長である建築家・谷口吉郎と佐藤栄作首相が面会し、政府協力のもと移築を進めるということで受け入れが決まった。

COURTESY: IMPERIAL HOTEL
それから約50年が過ぎた。日比谷公園から道路越しに帝国ホテルを眺め、もし今、ここにライト館の玄関部分だけでも建っていたらと想像する。本館2階の「オールドインペリアルバー」に残された、旧ライト館の壁画を横目にグラスを傾け目を細めると、かつてのライト館の中にいるような錯覚を覚える――。建築家・谷口吉郎が意匠を手掛けた「ホテルオークラ東京」本館(1962年竣工)も保存を訴える声が世界中から上がったが2015年に閉館、その後解体され2019年に新ホテルが完成し、かつてのロビー部分のみが復元された。解体・復元が日本の建築保存のお家芸だと思いたくないが、元々の場所で建築を使いながら保存することの難しさを表すエピソードである。