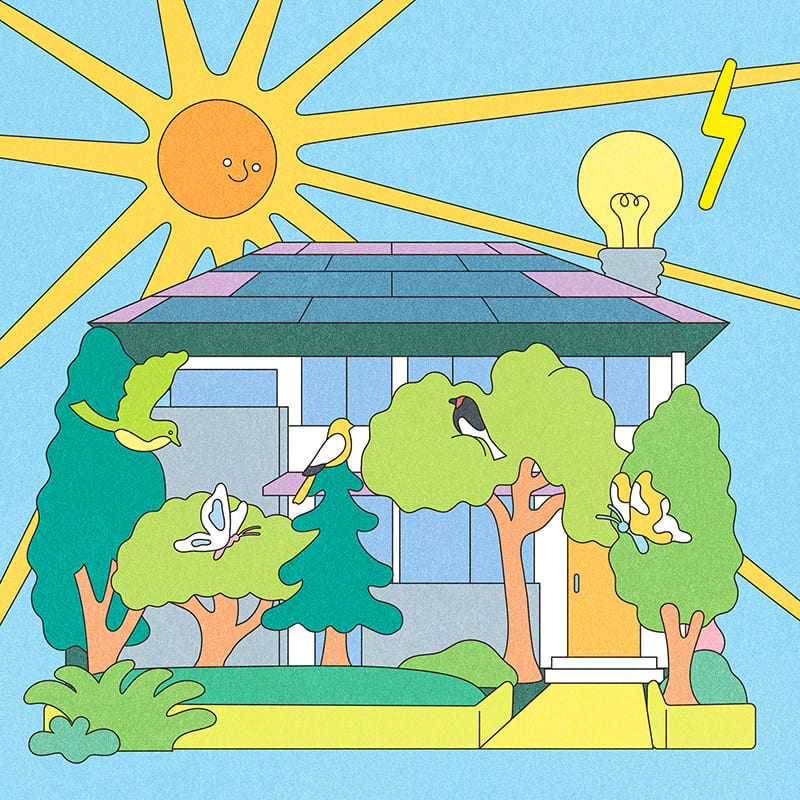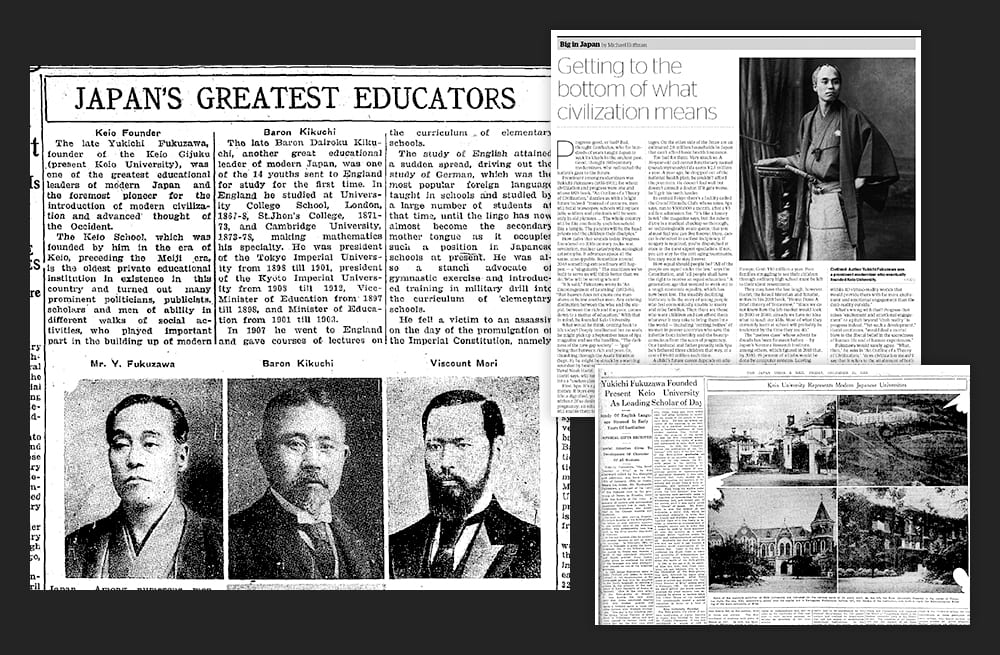November 25, 2022
人々の生活と共に発展し続ける、沖縄の焼き物

PHOTO: KOUTAROU WASHIZAKI
高畑伸也
1976年、兵庫県生まれ。2002年沖縄へ移住。2003年、金城敏男窯で修行。2005年、<一翠窯>設立。現在、読谷村とコザに工房を持つ。東京、台北、香港、バンコクなどで個展を行う。
https://touki.biz/

沖縄の伝統工芸品のなかで、日本の若い世代に人気があるのが器をはじめとする陶器だろう。沖縄の言葉で“やちむん(焼き物)”と呼ばれ、日常使いの比較的リーズナブルな価格のものが多いのが特徴だ。
沖縄で焼き物が始まったのは14~15世紀の琉球王朝の頃だと言われている。17世紀に入り琉球王朝が江戸幕府・薩摩藩の支配下に入ると、薩摩から招聘した朝鮮陶工により沖縄へ製陶技法が伝えられ、本格的な陶器の生産がはじまることになる。
現在、経済産業省から日本の伝統的工芸品に指定されている沖縄を代表する焼き物が<壺屋焼>だ。壺屋は現在の那覇市中心部にある地区。17世紀後半に首里王府が陶工たちを移住させたことでこの地で陶器の生産が始まり、瓦をはじめ、皿などの日用雑器や儀礼用の酒器などがつくられていった。
明治に入ると、<壺屋焼>は本土で大量生産された安価な焼物に押され生産が下火になる。しかし大正時代に入ると、その美しい色と大胆な絵柄が注目され、柳宗悦、河井寛次郎らによる「民藝運動」(庶民の生活の中から生み出された日用品に美的価値を置き広める運動)に見いだされる形で脚光を浴びることとなる。そして迎えた太平洋戦争。地上戦が行われここ沖縄では那覇も例外ではなく、市街の9割が壊滅的な被害を受けた。

沖縄県中頭郡読谷村字長浜18 Tel:098-958-0739
営業時間 9:00~18:00 12/31〜1/3のみ休み。
PHOTO: KOUTAROU WASHIZAKI

金城次郎の作品は、大胆に魚や蝦などが描かれているのが特徴だ。
PHOTO: MINAMI NAKAWADA
そんななか壺屋地区は奇跡的に破壊を免れた稀有なエリアだった。しかし戦闘終結すぐの那覇は米軍の占領下にあり住民の立ち入りは禁じられていた。住民は民間人収容所に入れられ、戦火で家財道具も失ったため生活に必要な食器すら事欠き、空き缶や瓶を割った物で代用しているような状況だったという。当時、米軍の諮問機関であり、沖縄住民の代表会議体でもあった「沖縄諮詢会」は、陶工や建設業者が壺屋に戻れば直ぐに陶器の生産を開始できる、だから一日も早く居住できるように取計ってもらいたいと米軍に働きかけた。
1945年11月、各収容所から壺屋出身の職人や建築作業班が集められ、100名を超える人々が壺屋に入域した。この時のひとりに、後に沖縄県人初の人間国宝となる金城次郎(1914‐2004)がいた。壺屋地区への入域から1か月後の12月。街ではいくつもの窯に力強い炎がともされ、煙が立ち上った。那覇の戦後復興はここ壺屋から始まったのだ。
その後、このエリアを起点に都市化が進み、煙の問題が浮上することとなる。1970年代になると薪窯の使用が規制され、登り窯の運営も困難となってきた。これを受け1974年、金城次郎は、米軍の接収が解け返還された読谷に窯を移した。これが現在も観光地として知られる読谷の「やちむんの里」のはじまりだ。。
近年、やきものを作り手は、沖縄県人ではなく本土出身者も多い。私たち取材班は色鮮やかな器で特に若い女性から人気の<一翠窯>を訪ねた。この窯を2005年に、29歳で設立した高畑伸也も沖縄出身者ではない。愛媛県で育った彼は20代前半にアジア放浪の途中で沖縄の器に出会い、2003年、人間国宝・金城次郎の息子、金城敏男(1936‐2016)の窯に弟子入り。ここから本格的に器づくりをはじめた経歴の持ち主だ。「きれいな花を見たら救われる気持ちになる。そんな生活を彩ることができる器をつくりたい」と語る。
沖縄の戦後復興を陰で支えた焼き物は、戦後約75年を迎えた今、新たな感覚がプラスされ、私たちの生活を今まで以上に、より豊かなものにしてくれることだろう。