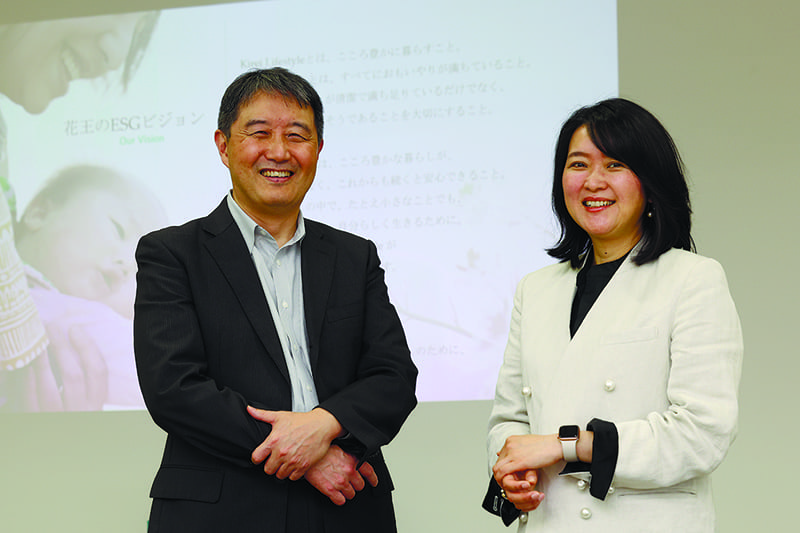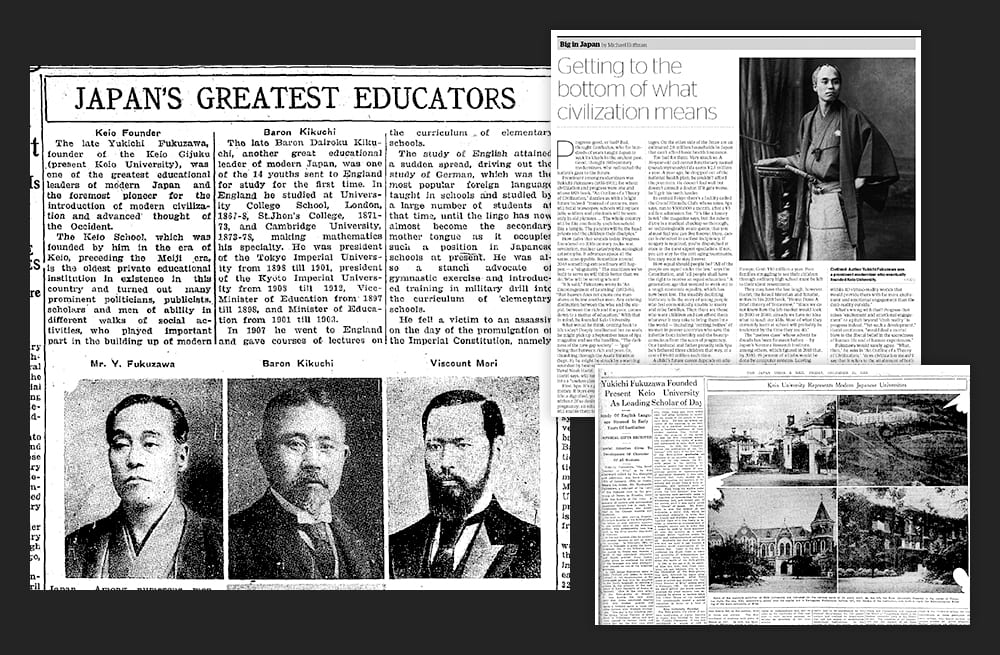September 27, 2021
環境と向き合い作品をつくる注目の芸術家に迫る。

PHOTO: SEITARO IKEDA / COURTESY: ART FOR SDGS: KITAKYUSHU ART FESTIVAL IMAGINING OUR FUTURE
昨今、現代美術を取り巻く状況はますますマーケット偏重主義が進み、オークションやアートフェアを意識した作品制作やロビー活動に走る作家まで現れるほどだ。一方で、アートバブルに沸く業界の喧騒とは一線を画し、独自のライフワークの探求や人類の未来を見据えた社会実験に取り組んできた作家たちがいる。なかでもテクノロジーやフィールドワークを生かし、自然と人間の関係性と喫緊の環境問題に向き合う3組のアーティストを紹介したい。
2021年春、元森美術館館長・南條史生がディレクションするサステイナビリティをテーマにした芸術祭「北九州未来創造芸術祭 ART for SDGs」が開催された。展示作品の中で際立っていたのが、田中浩也研究室+METACITY(青木竜太)による“人新世の社会彫刻”《Bio Sculpture》。森の深部から採取した土壌成分を赤玉土や籾殻などの自然素材を用いて3Dプリンターで再生し、無機質な都市空間や砂漠化した地域に移植するための装置だ。土壌はやがて種子や微生物により活性化し、森に宿る生態系が可視化される。

©SHUJI YAMAMOTO

©YUNA YAGIi
METACITYとは思考実験とプロトタイピングを通して「あり得る都市」の形を探求するリサーチチーム。代表の青木竜太が2021年夏、千葉県幕張市の日本庭園を舞台にキュレーションした「生態系へのジャックイン」展でも、アーティストや研究者、SF作家、建築家などが自然・テクノロジー・社会といった我々を取り巻く環境に対峙する作品を発表した。もはや袋小路に陥った文明社会を検証し、新たなパラダイムによる変革の可能性を探る彼らの取り組みには緊急性を帯びた切実な発想があり、鮮烈な刺激を受ける。
写真家・八木夕菜は、長崎県雲仙市で30年あまり有機農業と種の自家採種を営み、在来種・固定種の野菜の種を守る岩崎政利の活動に着目。気候変動や市場原理に翻弄される種子の問題に静かな一石を投じようとする。開催中の「KYOTOGRAPHIE 京都国際写真祭2021」では、通常は非公開の建仁寺両足院で本作を展示している。
山本修路は熟練の庭師の見識を生かし、青森県十和田市など各地でフィールドワークを行ってきた。林業の持続可能化への森林生態学的考察、米作りから携わる酒造り、イタヤカエデの新陳代謝の観測に伴うメープルシロップ作りなど、一個人として自然と接する全ての活動は「自然と人間との関わりを角度や距離を変えて体験し見る取り組み」なのだ。
アートを媒介とした表現者の自発的な取り組みには、時に人々の意識を覚醒させ、持続可能な社会への実践を喚起する「目ウロコ的」視点がある。不穏でしかない未来に明快なビジョンを提示してくれるクリエイションの力に今後ますます注目していきたい。