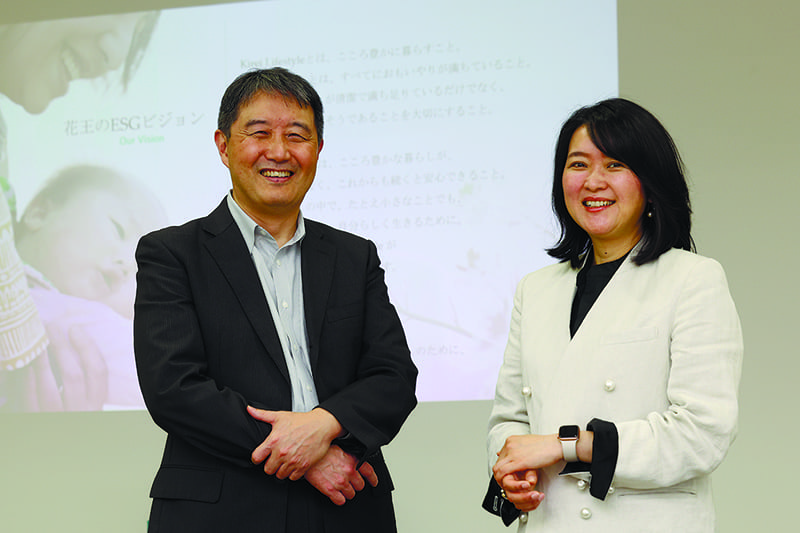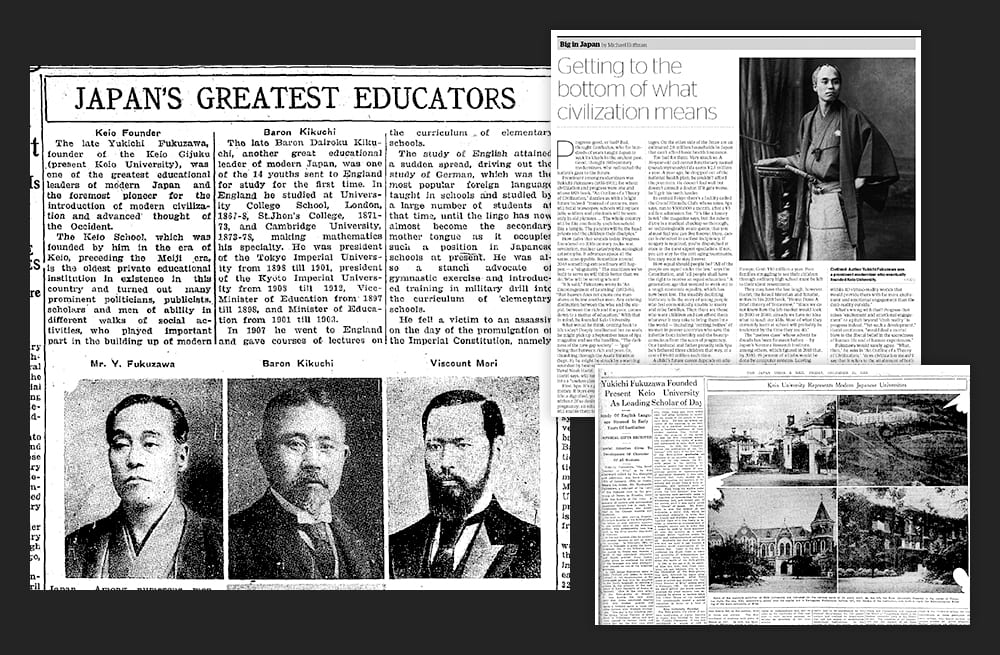August 29, 2025
【コマツ】次世代建機とインフラ整備、全方位で貢献

Komatsu’s strong points
1.CDP 2024年版の「気候変動」「水セキュリティ」でAリストの評価
2.低燃費・ハイブリッド・EV・燃料電池・水素エンジンと全方位で開発
3.給水素などのインフラ整備やICTを駆使したソリューションにも注力
4.大手鉱山企業との次世代機械の共同開発や「スマート林業」にも取り組む

日本を代表するサーキット「富士スピードウェイ」で2025年5月30日、「スーパー耐久富士24時間レース」が開催された。
市販車に近いツーリングカーで長距離を走る伝統的なレース。その会場で、レースに似つかわしくない“クルマ”が注目を浴びていた。水素で動く「ショベルカー」である。
展示されていたのは、日本の建設機械(建機)大手、小松製作所(コマツ)の試作機。トヨタ自動車の水素燃料電池(FC)自動車「MIRAI」の発電装置「FCスタック」が搭載され、水素が生み出す電力が油圧ショベルと本体を動かす。
排気ガスはゼロ。水や水蒸気しか排出しない、まさに未来の“働くクルマ”である。この試作機は、カーボンニュートラルを目指すコマツの取り組みのごく一部に過ぎない。
世界の建機業界をリード
コマツは、油圧ショベルやホイールローダ、ブルドーザ、鉱山などで活躍する大型ダンプなどを製造・販売する。2024年度の売上高は4兆1044億円。海外売上比率は90%を超え、今や米キャタピラーに次ぐ世界2位の建機メーカーとしてグローバルで名を馳せる。
同時に、建機業界ではサステナビリティ先進企業としても名高い。
2025年2月、国際非営利団体「CDP」が公表した2024年版でコマツは、「気候変動」で9年連続、「水セキュリティ」で5年連続となる「Aリスト企業」に認定された。
世界の建機メーカーでは、日本の住友重機械工業が2024年版の気候変動でAリストに入っているが、ダブルAとなったのはコマツだけ。世界の建機業界をサステナビリティでもリードしている。
コマツは2021年4月、創立100周年を機にコーポレートアイデンティティーを定め、「私たちの存在意義」として「ものづくりと技術の革新で新たな価値を創り、人、社会、地球が共に栄える未来を切り拓く」と明文化した。
同年にはサステナビリティ経営の更なる推進を目指す基本方針も策定。2050年までにScope3も含めCO2排出を実質ゼロとするカーボンニュートラルへの挑戦も宣言した。
大量の軽油を燃料とする建機は、CO2を主とする温室効果ガス(GHG)を吐き出す。コマツが排出するGHGのうち、Scope3の顧客による「製品使用(カテゴリ11)」はじつに87.4%も占めている。
この部分も含め、GHGの排出を実質ゼロにするためには、抜本的に建機業界の構造を転換する必要がある。コマツは「全方位」の姿勢で、この難題に挑戦している。

PHOTO: OSAMU INOUE
進む建機の低燃費化
「乗用車とは違い、建機はいろんな大きさがある。ハイブリッドなのかバッテリー駆動なのか。水素でもFCなのか水素エンジンなのか。あるいはケーブルで電源供給するのか、動力源を絞りきれてない状況。だから全方位で全部トライしています」。コマツでサステナビリティ推進本部長を務める出浦淑枝執行役員はこう話す。
2008年、コマツはハイブリッド油圧ショベル「PC200-8」を世界で初めて市場投入。政府統計によると、日本では建機保有台数の約75%を油圧ショベルが占めるとされており、その中でも売れ筋の中型をハイブリッド化した。「まず最も売れる機種から世の中に出したのは英断だった」(出浦執行役員)。
車体旋回の減速時に生じる回生エネルギーを蓄電し、エンジン加速時にアシストする独自機構で、ディーゼルエンジンで駆動する従来型に比べ約25%の燃費低減を実現。その後、ハイブリッド油圧ショベルのラインナップは増え、国内では最多となる計16型式が国土交通省の「低炭素型建設機械」に認定されている。
一方でコマツは電気のみで駆動する油圧ショベルの市場投入も進めた。2023年12月、バッテリー式と有線式の電動油圧ショベル計7機種について、国土交通省が新設した「GX建設機械認定制度」の初回認定を取得している。
従来型の低燃費化にも余念がない。ディーゼルエンジン駆動の油圧ショベルに加え、ブルドーザ、ホイールローダなども省エネルギー性能を高めており、燃費性能の優れた建機として国土交通省が認定する「燃費基準達成建設機械」にはコマツから25型式が選ばれている。
コマツは、建機や鉱山機械、林業機械などの製品が稼働する際に排出するCO2を2010年度比で2030年度までに50%削減する目標を掲げている。すでに2023年度、2010年度比で22%のCO2削減を達成しており、低燃費化は順調に進捗している。
これらに輪をかけるように、水素への取り組みも加わる。
「移動式給水素システム」の提案
トヨタ自動車のFCスタックが搭載されたFC油圧ショベルは、2023年5月から実証実験が進められている。高圧水素を充填する水素タンクもトヨタが供給。発電した電力が油圧ポンプを駆動し、それを360度旋回や最高時速5.5kmの走行などの動力としている。自動車最大手の技術力と、コマツ独自の機構が組み合わさった最新の建機だ。
同時に、水素を燃料とした内燃機関、水素エンジンの活用も進む。2025年2月、コマツは鉱山機械の主力機種である最大積載量約92トンもの大型ダンプトラック「HD785」に水素専焼エンジンを搭載したコンセプトマシンの実証実験を開始した。大型ダンプに水素エンジンを搭載するのは世界初の試みだ。
低燃費化、電気、ハイブリッド、燃料電池、水素エンジン……。あらゆる可能性を求めるが、“全方位”はこれらの車両開発にとどまらない。
作ることはできても、使うことができなければ意味がない――。コマツの視線は、燃料補填など実際の使用環境全般に向いている。サステナビリティ推進本部環境管理部の間宮崇幸部長(工学博士)はこう話す。
「乗用車と違い、建機や鉱山機械は山奥で使うこともあります。インフラを整えない限り、持っていったところで使い物にならない。だから車両開発だけではなく、トータルで考えていかなければ普及はしません」
山奥の現場には建機向けの充電スタンドもなければ、水素ステーションもない。この大きな課題に対してもコマツは向き合い、トヨタと一つの解を見出そうとしている。
冒頭で紹介した富士スピードウェイ。そこでコマツとトヨタ自動車は共同会見を開き、トヨタが提案している「移動式給水素システム」を明らかにした。トヨタ自動車の中嶋裕樹CTOが当日語ったのは、現場までトヨタのピックアップトラック「ハイラックス」の荷台に水素を載せて運び、FC油圧ショベルなどの「ミニ水素ステーション」とするアイデア。ハイラックスの移動でCO2は排出されるが、ある顧客のケースで試算したところ、年間約51トンが約1トンまで削減可能だという。

PHOTO: OSAMU INOUE
「スマートコンストラクション®」へ昇華
“全方位”が向く方向はまだある。現場でどう効率的に稼働させるか。その「ソリューション」にも力を入れていると間宮部長は言う。
「例えば、作業工程を計算すれば短時間の稼働で済むとか、あえて山の地形を整えてルートを確保したほうが移動のロスが出ないとか、稼働管理・運行管理の最適化によってもCO2を減らすことができます」
車両開発やインフラ整備など「ハード」面での研究開発に対して、「ソフト」面でもサステナビリティに貢献していこうという試み。その歴史は長い。
2001年、コマツは「Komtrax(コムトラックス)」というGPSを利用した機械稼働管理システムを標準搭載とした。機械の位置情報、稼働時間、燃料消費量、故障履歴などを遠隔でモニタリングできる当時としては画期的なシステム。盗難防止もさることながら、保守・メンテナンスやより効率的な稼働計画など、顧客にあわせた提案ができるようになった。そこには当然、燃料消費量の改善、つまりCO2排出量の削減のサポートも含まれる。
2013年には、位置情報などを利用し、世界で初めてブレードを自動制御する機能を搭載した「ICTブルドーザー」を、翌14年には世界初のセミオート制御機能を搭載した「ICT油圧ショベル」も市場投入した。
「現場でのCO2削減においてエポックメイキングな製品」と出浦執行役員。「ブルドーザの軌道や刃先の制御を図面通りに自動的に行うICT機械は、それ自体すごいことですが、どんなオペーレータが作業をしても確実に燃費が良くなることが画期的なのです」と話す。社内の試算ではICT機械の導入で約25〜30%の燃料削減が確認された例もあるという。
そして2015年、KomtraxとICT機械という礎は、さらに効率化の範囲を拡大した「Smart Construction®(スマートコンストラクション®)」へ昇華した。
ICT機械と、ドローンや3Dスキャナーによる「現況地形計測」を組み合わせ、現場の作業効率化とプロセスの「見える化」を実現するソリューション。これにより、施工や作業現場の全体を見渡し、測量から検査までプロセス全体を通した効率化を提案できるようになった。CO2削減効果に加え、労働力不足の課題も解決できるとあって、世界でのスマートコンストラクション®の導入現場数は、2025年6月末時点で累計4万9223件に達している。
林業機械で山の再生にも貢献
こうしたハード・ソフトが一体となったソリューションこそが、顧客企業のCO2削減に欠かせない。そうコマツは考えている。
だからこそ、2025年4月から始まった3カ年の中期経営計画(中計)「Driving value with ambition 価値創造への挑戦」では、コマツが目指すありたい姿を「安全で生産性の高いクリーンな現場を実現するソリューションパートナー」と再定義した。
ここには顧客企業と「パートナーでありたい」という思いも込められている。その思いを象徴するのが2021年に発足した「コマツGHGアライアンス」だろう。
鉱山におけるGHG削減を加速するため、リオティントやBHPといった世界有数の鉱山企業12社とともに次世代の鉱山機械の企画、開発、テストなどを共有する枠組み。最初のターゲットは「パワーアグノスティックトラック」。バッテリーや燃料電池、水素エンジンなど、いかなる動力源でも稼働可能な超大型ダンプトラックの開発を進めている。
出浦執行役員は「製品をお渡しするのではなく、一緒に開発するということ。毎年、大規模な展示会でイベントを開催しており、今年も様々な取り組みを通じて、アライアンスの可能性を広げていきたい」と新展開に含みを持たせた。
2025年からの中計では、スマートコンストラクションや「AHS(無人ダンプトラック運行システム)」などのソリューションを更に進化させるとしている。また、これまでも取り組んできた林業機械事業も、より強化されることとなった。出浦執行役員はこう説明する。
「最近の当社は、従来からの建設、鉱山にプラスして、林業にも注力しています。アピールしたいのは森の再生。林業機械はもともと伐採して運び出すための機械でした。でも、切って終わりではなく、上手に切って、地ごしらえをして、効率的に植林するまでの循環を意識した製品のラインナップを拡充しているところです」
この取り組みは、ドローンなどを活用したスマートコンストラクションの林業版「スマート林業」として、林業のDX化に寄与しつつある。全方位でのサステナビリティへの貢献。その拡大と進化は止まらない。
創業時から根付くサステナビリティ
出浦淑枝
執行役員 サステナビリティ推進本部長
1921年、石川県小松市で「小松製作所」として創業されてから、コマツは今年で104年目を迎えます。創業者の竹内明太郎はもともと、小松市近郊にあった銅が掘れる鉱山のオーナー。そこで働く機械を作ろうということで設立しましたが、ほかの狙いもありました。
それは、鉱山は掘り尽くしてしまったら終わりだけれども、機械を開発していく「技術」やそれを可能にする「人材」は地域に持続可能な発展をもたらす、というものです。
竹内は「海外への雄飛」「品質第一」「技術革新」「人材の育成」を創業の精神として掲げました。その精神は今でも「コマツウェイ」として受け継がれていますが、これらの精神は持続可能な価値を後世に遺すためのものでもあったのです。
つまり、コマツにとって「サステナビリティ」とは、降って湧いた概念ではありません。100年以上前の創業時から、当社のDNAのようなものであり、経営のあり方や従業員に根付いています。
コマツは創業の地を超え、世界で商売をさせていただくまでに成長しました。今、我々が考えるべきは、地域の持続可能な発展にとどまらず、世界の持続可能な発展。自然環境のサステナビリティ、社会全体のサステナビリティのために取り組むことは、当社にとって自然なことであり、その「責任」もあります。
また、当社の製品を使ってくださるお客様も、社会からサステナビリティへの対応を求められています。お客様のためにも、当社はより環境負荷の低い製品の開発や、その普及について努力しなければなりません。
特に、鉱山開発を手掛けるお客様からの要求は年々、厳しくなってきています。サステナビリティに配慮した製品開発に参画してくださるお客様もいます。一方で、コストの問題からなるべく燃料を使いたくないと考え、低燃費の製品を求めるお客様も存在します。
これからも技術をより向上させ、そういったお客様、あるいはステークホルダーの皆様と、安全で生産性の高いクリーンな現場を一緒に作っていく。一緒に新しいマーケットを作っていく。人と社会と地球と共に栄える未来のために、最大限の貢献をしていければと思っています。