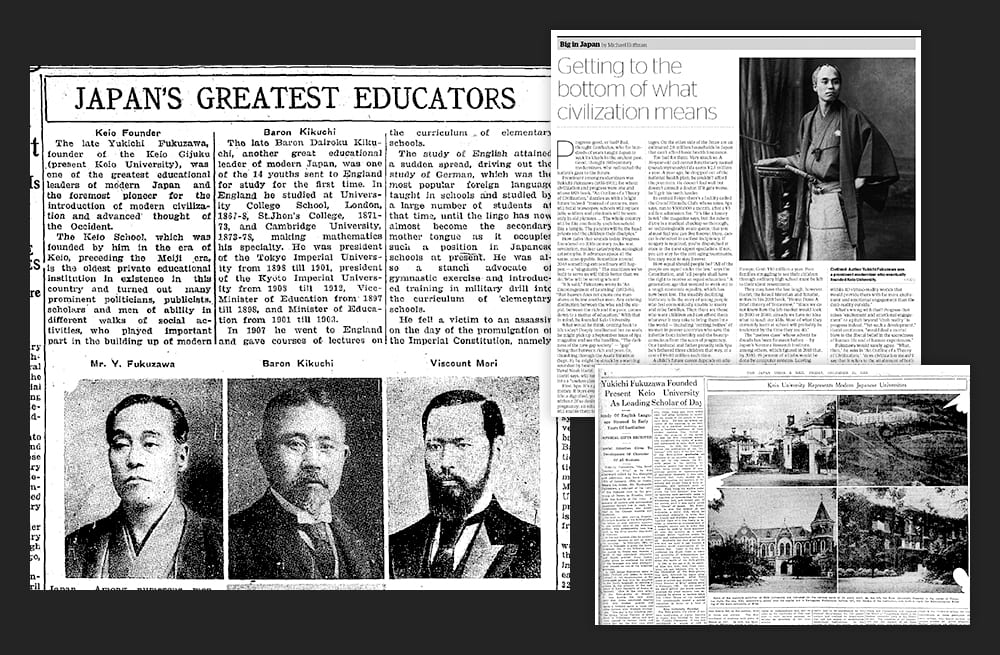August 29, 2025
Vol. 51: FROM THE EDITOR

相撲は日本の国技といわれる神事であり、伝統文化のひとつです。その起源は古く、日本最初期の書物である古事記(712年)や日本書紀(720年)にも、力くらべの神話や伝説がでてきます。奈良時代(710年~794年)や平安時代(794年~12世紀末)になると、相撲はその年の農作物の収穫を占う祭りの儀式として毎年行われるようになり、宮廷の年中行事にもなりました。
土俵入り、番付表、化粧廻し、髷(まげ)など、日本ではお馴染みの、テレビ中継などでも見られる現在の「大相撲」のスタイルになったのは、江戸時代(1603年~1868年)になってからのことです。力自慢の者の中から、相撲を職業とする人たちが現れ、江戸時代中期には日本全国で相撲が興行されるようになりました。その中からスター力士も現れ、相撲は歌舞伎と並んで一般庶民の間で人気の娯楽となったのです。
21世紀の今、大相撲には数多くの外国人力士が存在し、8名もの海外出身の横綱が誕生しています。また、今年2025年10月にはロンドンで、来年6月にはパリで相撲が行われます。今回は日本の伝統文化のひとつ「相撲」を巡るサステナビリティに迫ってみたいと思います。