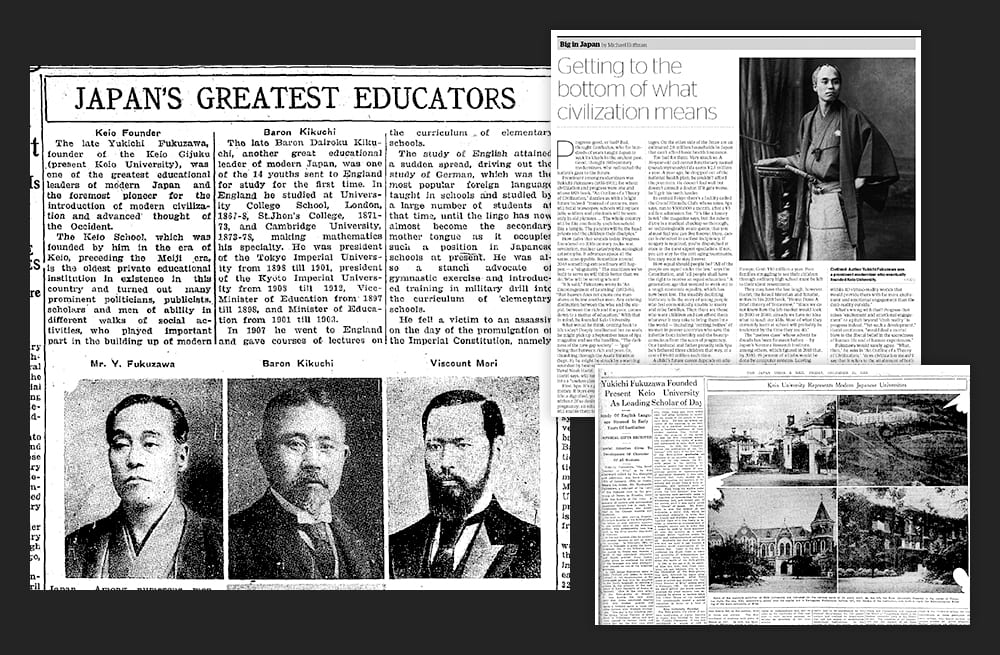February 21, 2025
芸術家の醍醐味は「多様な考え方を広げる」こと。

PHOTO: TAKAO OHTA
かわいらしいヤドカリが美しい透明の貝殻に入った作品や、ビーバーに削らせた木を改めて仕立て直し彫刻作品にしたりと、現代美術作家・AKI INOMATAが生み出す作品の数々は動物とのコラボレーションの賜物だ。だがその愛らしい生き物たちを用いた作品の根底には、人間社会が作り出したシステムや既成概念への問題提起など様々な“何か”が流れている。
例えば、『やどかりに「やど」をわたしてみる』という作品。ヤドカリは体の成長に伴い、より快適な「やど」が見つかると引っ越しを行うという習性がある。そこでINOMATAはCTスキャンで自然の貝殻の内部構造を計測し3DCGで制作したデータを3Dプリンターで出力する手法を用い、「やど」を制作。その「やど」の頂部にはNY、パリ、香港、東京などそれぞれの都市のランドマークとなる建築をかたどった。世界各地の都市を模した「やど」へ次々と引っ越しをするヤドカリの姿は、今ニュースでも度々流されている移民や難民を想起させ、そんな人々の姿にも重なり合う。人のアイデンティティとは何か、見かけの在りよう、国籍の在りようとは何かを、考えさせる作品なのだ。

© AKI INOMATA / I Wear the Dog’s Hair, and the Dog Wears My Hair,2014
この作品はINOMATAが、東京にある在日フランス大使館の、解体される前提の建物を使って期間限定で行われた展覧会『No Man’s Land』(2009年)の出展を期に制作をスタートしたものだ。 在日フランス大使館の建物は2009年に解体され、隣接する土地に新しい大使館が建てられた。その旧・在日フランス大使館の土地は、2009年10月まで「フランス」だったが、以後60年間定期借地に出されることで「日本」となり、その後また返還され「フランス」になるという。同じ土地であるにも関わらず、国が入れ変わる事実と、中身は同じでありながら、背負う「やど」によって、すっかり見た目が変わってしまうヤドカリ。彼女は2つの事柄に共通項を見出しこの作品を生み出したのだ。
もうひとつ印象的なのがビーバーが削った木を元に制作する『彫刻のつくりかた』という作品。INOMATAは5つの動物園に依頼し、ビーバーの飼育エリアに角材を設置させてもらう。その後、ビーバーがかじった角材を集めると、そのフォルムは美しく、彼女には人間のつくった彫刻のようにも見えたという。そこでビーバーがかじり残した形を元に、彫刻家と切削機械にそれぞれ人間大のスケール(現物の3倍)で模刻してもらい作品としたのだ。ビーバーがつくったものを人間と機械が真似て作る。となると、この作品の作者は人なのか、機械なのか、あるいはビーバーなのか?


AKI INOMATAの作品『やどかりに「やど」をわたしてみる』(2009-)。CTスキャンで巻貝の貝殻の内部構造を計測し、3DCGで制作したデータを3Dプリンターで出力する手法を用い、「やど」を制作。その「やど」の頂部にはパリ、東京など都市のランドマークとなる建築をかたどった。世界各地の都市を模した「やど」へ引っ越しをするヤドカリの姿は、移民・難民などを想起させ、人のアイデンティティとは何か、国籍の在りようとは何かを、考えさせる作品。
©AKI INOMATA / Why Not Hand Over a “Shelter” to Hermit Crabs? -Border-(2009-)
「私は生き物がもつクエイリティビティに興味があります。例えばビーバーであれば、樹木でダムや巣を作り水を貯め、その周辺環境まで変えてしまいます。まずこのような習性をリサーチし作品づくりに取り組みました。今回着目したのはビーバーがかじった木材ですが、角材に残されたビーバーがかじった痕跡は人間がつくる彫刻作品のようです。いわばビーバーが作者です。ですが、この痕跡はビーバーは木の節などの堅い部分を避けてかじった結果だとも考えられる。もしそうであるなら、この木のフォルムを作り出しているのは、ビーバーではなく、木そのものではないか、この作品の作者は木なのではないかとも考えられます。では何を行為の主体=作者と見るべきなのか? その行為の主体は誰なのか? そのようなことを考えさせる作品になっています」。INOMATAは説明する。
彼女が芸術作品を通じ探求していきたいと考えているのは、“人間が人間のためだけを考えていくのではない世界観”だという。だがINOMATAが当初、大学時代にテーマにしていたのは、自然環境といかに接続するか、だった。
「東京生まれ、東京育ちで大自然にあまり触れてこなかったことから、当時は自然現象を展示室内に持ち込むような作品をつくっていました。藝大の修了制作でつくった作品は、自然現象をデジタルで制御して天井から床に水の波紋やポツポツと雨垂れが落ちるような現象が投影されるという作品。ですがこのような作品は、私が違和感をもっていた都市社会において自然をコントロールしたり、生き物を排除したりするようなことを再生産してしまう側面があるのではと感じました。それであれば自分ではコントロールができない他者とコラボレーションから作品作りをしてはどうかと考えたのです。そのような考えもあり2009年の在日フランス大使館での展示の際、ヤドカリの作品が生まれました」。
最後に、彼女自身が作家として、または一個人として、女性だから不利益を被ったことがあるかどうかについて聞いてみた。彼女は、利益・不利益という枠組みでは考えていないと前置きしつつ、アーティストができるのは「多様性を示すこと」だと考えを述べた。
「アーティストは作品を通じ多様性を示すことで、人々の世界観や価値観を広げていくことが醍醐味だと思っています。私の場合は、人間界だけではなく自然界も含めた様々な生き物の多様性や、人間中心主義を変えていこうということが作品づくりのテーマになっています。アーティストが訴えるものはそれぞれですが、共通しているのは既成概念にとらわれず、世界観を拡張していこうとすること。世界の見方が広がっていくことで、多様性を認めるような考え方が生まれ、個人が生きやすい社会をつくる一助になっているのではと思います」。

©AKI INOMATA / How to Carve a Sculpture,2018- / Photo: Naomi Ito, Production Assistance: Izu Shaboten Zoo


©AKI INOMATA / Mutual Aid. Art in collaboration with Nature 31,Oct 2024 – 23 Mar 2025, Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea Photo:Sebastiano Pellion di Persano
AKI INOMATA
現代美術作家 1983年生まれ。2008年、東京藝術大学大学院先端芸術表現専攻修了。東京在住。人間以外の生きものや自然との関わりから生まれるもの、あるいはその関係性を提示している。アンモナイトとタコを長大な進化の時を超えて出会わせる作品『進化への考察』など、生きものと共に制作した作品を多く発表している。作品の主な収蔵先に<MoMA(ニューヨーク近代美術館)>、<南オーストラリア州立美術館>、<金沢21世紀美術館><京都国立近代美術館><北九州市立美術館>などがある。https://www.aki-inomata.com/